 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
(題字は石川啄木「悲しき玩具」直筆ノートより、写真は啄木が過ごした現在の小樽と小樽水天宮境内の歌碑) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
明治三十五年日誌 石川啄木 啄木日記 石川啄木 啄木日記の原本は、次のものを使用しています。 発行所:株式会社岩波書店 書 名:啄木全集 全17冊のうち、第13集 発行日:昭和36年10月10日 新装第1刷 なお、筑摩書房版全集と照合し、不突合の場合は調査、不明の場合は筑摩版を採用しました。 原文で使用している仮名遣いや送り仮名は極力原文どおりとしていますが、漢字はウェブ表示上問題があると思われる文字については、現在使われている文字またはかなに置き換えていますのでご了承ください。 明治三十五年日誌 秋韷笛語 三十五年秋 秋韷笛語 白蘋 秋韷笛語 《白蘋日録》 序 運命の神は常に天外より落ち来つて人生の進路を左右す。我もこ度其無辺際の翼に乗りて自らが記し行く鋼鉄板上の伝記の道に一展開を示せり。 惟ふに人の人として価あるは其宇宙的存在の価値を自覚するに帰因す。人類天賦の使命はかの諸実在則の範に屈従し又は自ら造れる社会のために左右せらるるが如き盲目的薄弱の者に非ず。宜しく自己の信念に精進して大宇宙に合体すべく心霊の十全なる発露を遂ぐべき也。運命は蓋し天が与へて以て吾人の精進に資する一活機たるのみ。されば余輩は喜んでその翼に鞭うつて人生の高調に自己の理想郷を建設せんとする者也。 呱々の声をあげてより十有七年。父母の膝下を辞して杜陵の空に学ぶこと八星霜。前途未だ漠として浮雲に入る。この秋流転の水流に従つて校を辞し友とわかれ双親とはなれ故山を去り恋ふ子の美しき面影とさへわかれて孤影飄然東都に出づ。嗟乎、何人かよく遊子胸奥の天絃に知音たる者ぞ。 秋韷笛録はこの旅出の日より起したる日誌也 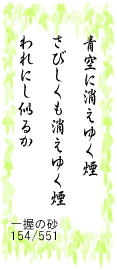 裂かば花に、砕かば琴の夢追ふ子追ふて旅する命の秋よ。 天琴に誰かよき音の幸守らむ秋掩ふ雲にわかれて去ぬる。 明治三十五年秋 白蘋詩堂 装ひては 花の香による 蝶の羽 秋は韷れの 笛によろしき。 (※韷れ=おとづれ) 笛 語 十月三十日 朝。故山は今揺落の秋あはただしう枯葉の音に埋もれつつあり。霜凋の野草を踏み泝瀝の風に咽んで九時故家の閾を出づ。愛妹と双親とに涙なき涙にわかれて老僕元吉は好摩ステーシヨンまで従へたり。 かくて我が進路は開きぬ。かくして我は希望の影を探らむとす。記憶すべき門出よ。雲は高くして巖峯の巓に浮び秋装悲みをこめて故郷の山水歩々にして相へだたる。ああこの離別の情、浮雲ねがはくは天日を掩う勿れよ。遊子自ら胸をうてば天絃凋悵として腔奥響きかすか也。 南行して盛岡に下車し仁王の僑居に入る。 午後。朱絃藻外を訪ひ阿部兄とも談じたり。下の橋写真館にて岡山残紅兄と撮影しそれより共に片袖庵に蒼梧氏を訪ふ「透谷全集」を贈らる。 我が発程の急なるに皆驚く。 夜。阿部小野小沢三兄と共に加賀野に伊東兄を訪ひ別宴を張る。 青春の望みに憧るる者は幸ひなる哉。万づの勇と力皆これより生ず。吟身愁ひを知る者は聖なる哉。紛紜の胸中自ら清高の香あり。ああ高き者よ、汝の座は天上に設けられたり。 昨夜よりのつかれにて杜陵城下の終りの一夜を安らかに温かに眠りぬ。 ○ 若き我れにふるべき鞭のつよき神韷れゆくを笛によみすや。 神を仰ぎ道なる花にはぐれきよ何地向きてぞ我れ歩むべき。 十月三十一日 午前。湧くなる我血汐もかくては遂に溢れなん。別れなればの涙にわが恋しの君訪れ玉ひぬ。 まこと今日のみならじ。わかれなればとて永き宇宙の飄泛に永遠を友とすてふ愛の世に何の時か今日のみと云ふことあらむや。二つ並べる小笹舟運命の波にせかれて暫しは分るるとも又の逢ふ瀬は深き深き愛の淵の上に波なき安けさぞ尊からむ。東都の春の楽の音に共に目さめむもここ六ケ月のうち。ああさらば胸の轟きしづめて蘋の身の、世の大波に暫らくはひとり南せんか。 さは云へど胸掩う愁ひの聖なるぞ哀しや。うす紫にわが好む装ひしてあたたかき涙にくれ玉ふ恋の心のただずまひ。女神夕に星をうらむもかくやと許り、うつつなの境ひを辿る情を、男なればの我身辛くも涙を噛みぬ。 君よ「今日のみならず」の一言にこもりぬる二人の命ぞ崇く候はずや。骸は百四十里のかなたにへだつとも魂は常に聖なる宮の燭影にゆらぎに相抱かむ。かくて暫しのわかれを、天がけらむ理想の日に行くべき路程の駅路とこぞ思はめ。 タイムは飛ぶが如くすぎて。涙!!! 涙!!! 涙!!! かへらせ玉ひぬ。 故友阿部春雨氏の遺稿をわが君に托して保存することとしたり。 午後公園よの字橋側の高橋写真館にて阿部君らとユニオン会五人撮影す。
猪川箕人瀬川藻外細越白螽小林花郷岡山残紅の諸君来り談夕方に到る。今日は愈々上京の日なり。 五時行李を整へ俥を走せて海沼の伯母や姉等にわかれ停車場に至れば見送りの友人すでにあり。 薄くらき掲燈の下人目をさけ語なくして柱により妹たか子の君の手をとりつつ車中のわれを見つめ玉ふ面影!!! ああ如何にあたたかきみ胸ぞ。たとへ吾を送るに千人の友ありとするも何れかよくこの恋の君の一目送の語なくしてかたる紅涙にしく者あらんや。 五十五分、我はあはただしう友と別れの言を交はしぬ。汽笛一声、車は南に向つてなつかしき杜陵の地をはなれぬ。…… 夜の空のしめやかなるに想ひの車轟きて窓によれる我胸狂乱の嵐に乱れぬ。 かくて我はわかれたり。故関の秋の風に袂ぬらしつつ親しき友と、恋しき人と。 かくして我は哀々の夢に目さめぬ。悲しみの袖をあげて襲ひくる「別離」てふ感情はひしひしと我胸の奥深く征矢射込みたり。二つ三つの停車場すぐるは我のしらぬうつつのまなりき。黒き夜の幕に包まれたる杜陵城下の燦たる燈火はああはや暗に呑まれぬ。 吾は南に、人は北に。車窓によりて甚深なる瞑想に落ちたる吾はひたすらにこのわかれを思ひつづけぬ。今朝美しき涙の露にうるほしたるそのやさ眉の君、ああ今又静かなる新山祠堂の後なる室に泣きてやおはさむ。愛なる永遠の光を讃じてこの悲しきわかれの愁ひうち消さむとすれど、ああただ徒らに胸の威の抑へ難きを泣かしむるのみ。 汽車は絶えず進みぬ。十時には仙台を通過したり。花明の君や如何に、紫琴の君やいかに。誰かよく我がこの愁ひを知る者ぞ。 十一月一日 愁ひの一夜は那須野が原に明けぬ。ただ見る落秋の装ひ寥々として目もはるに大野の草雲に入るほとりかすかに筑波連山の靄をきて立てる身ゆ。曙の色わづかに東天にほのめくと見ればやがて雨そぼそぼと降り来ぬ。 うつつなの想ひにのみ百四十里をすぐして午前十時上野駅に下車し雨中の都大路を俥走らせて十一時頃小石川なる細越夏村兄の宿に轅下させぬ。 談つきずして夜遅くまで眠らず。出郷第一夜の夢はここに結びたり。 ○ 旅は君、胸の若きにふさはずよ乱れて雲の北にとき夢。 市に入りて名なきすぐせをはづべしや花の高きぞ風つよき者。 霜寒の筆の趣き市にたへずねがはく神の詩の花たびね。 さらば君さらば剣の犠をしもここなる市の人にさぐれとか。 地に咲かん花の命にうらぶれて市の夕の塵を辿る子。 めざす方におごりあるべき世と思ひ愛の帆章追ふて漕ぐ海。 杉にこもる祠夕べにそぼつ雨ぬるる袂に相よりし欄。 十一月二日 雨、 午前夏村兄と共に秋の歌つくらむとてならず。 細越白螽君の文杜陵より来る。ああ吾友よ。親しむべきは其あたたかき胸のうちなる哉。我は謝す。! 午後夏村兄と共に散歩す。小石川の地高燥にして繁ならず。友は秋の季に最も適せりとて称する事甚だし。小日向台に上る。 今わが腑観する大都よ。汝は果して如何なる活動をなしつつあるか。何ぞただ魔の如きのみならむや。吾はこの後心とめて汝の内面を窺はんか。 夜。小日向台三ノ九三、大館光氏方に移る。室は床の間つきの七畳。南と西に椽あり。眺望大に良し。 夏村兄に伴はれて机、本箱等種々買物す。故家への手紙認む。 友かへり夜静かにして旅愁あはただしう我心を襲ひぬ。 ああ我は永遠に目覚めたり。 ○ 人の胸に人の心臓を掩ひあへで乞ひしは秋の花にちる夢。 秋の胸の悲しみ細き雨の夕旅はかなげの吾は戸に立つ。 眼とぢて立つや地なる骸の世辿る暫しの瞬きよ恋。 小萩咽ぶ雨しめやかに黄昏れぬ愁ひて一人秋をゆく笠。 迷ひては秋の心を風にとひぬ百葉誘ふて何地へにぐる。 岩を踏みて天の装ひ地のひびき朝の光の陸奥(みちのく)を見る。(岩手山に登る) 十一月三日 天長節、曇天、 午前、買物、 端書認む(大井、金矢、瀬川、岡山、小林、猪川、上田、桜羽場、佐藤、片岡、石亀、田鎖、小野寺、高橋、海沼、田村、堀内、秋浜等の諸氏へ) 鉄幹氏へ上京報知す。 午後。本郷にて露子岩動君に逢ふ。野村菫舟*君を(本郷六丁目二十八日村方)訪ふて逢はず。一人忍ばずの池の畔より上野公園に上り日本美術展覧会見る。 陳套なる画題を撰んで活気なき描写をなすは日本画界の通弊也。こ度の展覧会にて注意すべきは洋画の描写方を日本画に応用したる作の二三あること他その中にて弁慶の図など少しく可なり。 画の外あらゆる美術品数千点を陳列したり。それらのうち吾目に付きたるは薬師寺行雲氏の石膏彫刻婦人裸体立像及び(作者忘れたり)銀製の武将乗馬して弓を射る像也。 前者は丈二尺五寸。美神の如き麗人の少しくうなだれて、胸に聖愁をたたへ恋の星に憧るらむたとしへもなきめでたき趣き、崇高なる真白の姿して限りなき景仰に値しぬ。 夜。抱琴原兄、及び金子定一君野村君等へ端書して上京を報じ山崎へも送る。 出京以来漸く少しく心落ち付きたれば杜陵なるせつ子の君へ手紙かきぬ。 迸しる涙のわりなき秋や、嘗而賜ひし歌の手巾にて溢るるを抑へつつ記しぬ。あはれ恋しの君わがこの文を読まば君もや温かき涙にくれ玉ふらむ。 二時就寝。 涙!!! (*筑摩書房版全集は「琴舟」。野村胡堂の雅号はこのころ「菫舟」) 十一月四日 空心地よく晴れ渡りたり。 午前。阿部小野小沢伊東四兄へ長き手紙認めたり。 咏歌。鉄幹氏より来翰。晶子女史御子あげ玉ひし由。 午後。牛込女子大学のあたりまで散歩す。 四時頃より野村菫舟君来り夕飯を共にし九時かへる。 友は云ふ。君は才に走りて真率の風を欠くと。又曰く着実の修養を要すと。 何はともあれ、吾はその友情に感謝す。 細越白螽君へ端書認む。 ○ いざさらば又のあしたの思出に叫ばん者よ詩の黄昏。 花枯れの友の世多き黄昏を天なる蝶の羽ぞ羨みし。 枝にふれて失せぬる風の行方しらに迷ふて落つる袖の葉か、森。 ○ 瞑る花の風にめざめし瞳上げてふと巨虹の光よぶ朝。 若くして人の世に見る才まねばずかくて胡蝶の羽摧く夕。 落つる月に秋は希望の袖小さし掩ふては胸の高調に泣くよ。 市の風に知りぬる秋の暮の色北に愁ひの雲ぞ尊き。 雲をささへ秋の色なる葉の巨樹影は夕日に長うも暮るる。 朝に夕にゑにしよ淡き川の風逢ふては橋の袂にわかる。 佇みてふと大川にまどひたり舟は秋野の風のせて行く。 落葉ふみて踏みてここなる森の路星おごそかに雲井を洩るる。 十一月五日 朝遅く起き急ぎ飯を了へて本郷の自炊に菫舟君を訪ふ。安村兄工藤兄も在り。 菫舟君と共に神田辺を徒歩し諸所の中学に問ひあはせたれど何れも五年に欠員なくて入り難し。故に始めの志望通り斎藤秀三郎氏の正則英語学校の高等受験科に入ることに思ひ定め規則書在学証書等貰ひ来る。 古本屋多き猿楽丁を通りて又自炊にかへり昼食。閑話して五時かへる。 食後夏村兄と日向台の暮色に散歩す。 本日午前金子君来訪せられし由なれど留守にて惜しきことしたり。 「校友に与ふるの書、落風秋語」かきそめたれど胸何とはしらず愁へて遂に筆投げぬ。 夜静かにして想ひの羽のみぞ北の空にかける。吾は友のなつかしきをほしと思ひぬ。乙女の美しきを恋しと思ひぬ。ああその人今如何に。 ○ 起てよ友、風の夕の百合折れぬかくてぞ秋は京に入りぬる。 愁ひぬれば古き軒端にかへりゆく魂の疾き羽の恋よ百四十里。 猛くして男の子の道に脆くして恋の細路に魂迷ふ夕。 雲の乱れ野の嘶ぎにわれさめで、秋風ただにたてがみながき。 駒やせて野に勇ましの秋もなしやみて立つ戸のほころびの袖。 すぎし日のすぎし想出さり乍ら我には永劫のうつくしき鞭。 せめて宵、唄の細音の野にあらば月に羊のめぐきもあらば。 西の日の栄に酔う子よふりかへれ秋つしま根は大ひなる虹。 封じ込めてそのさびしさの香に泣きしわれや山茶花京の秋寒。 碑によりて秋のゑまいのさびしさに遠のく雲に光見ぬ暮。 関を出でて望みもありし旅よおろか京の夕は秋にふさへる。 袖かみて四年なる血ぞあたたかき南に北に秋は似たるよ。 楽の音にさめむ暫しの暗の秋はみ袖の花の京の春待ち。 仰ぐ雲に光まばゆき詩の五洲鞭のそら音にぬる子起さむ。 星の世の花ぞ降りきて咲くべけれそのほほゑみの曙の園。(二首鉄幹氏の下へ御祝) 小さき神の幸のゑにしよ熱かき曙雲のよろこびの影。 想ひかへしまた釣舟花の夢に入るよ紅きもありしその袖の糸。 暮るる日を讃じて秋のたなごころ合はす暫しにはや血さびるる。 詩の袖に琴の細緒に幸しらず悟りて暗に消えにし友や。 人の世に人の心のあたひしらでさまよひ行きし果の太洋。 かくてただゆききする世の波のぬた月落ち行きて星かくろひて。 ふとさめし瞳とぢてぞ安かりし夢の行方の暗を思ひぬ。 涯もなう流れて水はかへり来ず神に終なる裁判否むよ。 待ちし春、待たるる春とめぐる地の年の大波かへる時なく。 暗無限今か終りの一呼吸の胸を覆ふぞと神にすがりし。 陰府の道に一人さめてぞ辿りゆく吾によるべき杖たまへたまへ。 小ささ神のこの世に生ひし香ぞ高う光あふるる曙よ今。(三首鉄幹氏の下へ祝ひとて) さめてねて詩にはぐまれん幸の君小さきゑがほぞ永劫に高かれ。 星の世の花の降り来ん園としるそのほほえみの盃の色。 砕けてはまたかへしくる大波のゆくらゆくらに胸おどる洋。(石の巻を懐ふ)二首 くるる雲をはてを何所としらずして洋覆ふ幕に想ひ入りぬる。 濁る波にただよひ出でむ想ひぞもうき艸つひに紅ゐならぬ。(十首出郷) 関を出でて何所としらぬ羽のちから行方なりとて暗指せし。 行く秋のちる葉憐み留めんとてあはただしうも追ふて出る郷。 秋の山のにしききて行く我なれば泣きまさざりしたらちねの胸。 踏む路のしもがれ草ぞわれによきかくてかへらむ日の草嫩葉。 虹の輪のたかき仰ぎてかへり見てかざすは秋の詩の袖なりし。 暫しさめて再び入らむ聖き夢ゆめはとこしへ幸あらむ者。 わかれなりとうす紫の袖そめて萬代われに望みかけし人。 枯葉見て星を仰ぎて幸の世のみじかかるべき旅をさぶしむ。 高き世の高きのぞみと思へばのこの旅立に辛かりし涙。 み文みてその夜がたりを思ひ出で思ひかへして涙に朽つる。(花郷兄へ) (以上は鉄幹氏に送れり) 十一月六日 全晴 朝。小林花郷君の書状は杜陵より、原抱琴兄の端書は芝より来る。 秋は冷たく光なく白壁を暗にさぐる如きとやああわが故郷!!! 健在なれよ友!
一日詠歌にくらす。夜に入りても写真側よりはなし難う覚えぬ。鉄幹氏に送るべき歌稿と手紙認む。 想ひは家郷にあり。 十時ごろ岡山残紅兄のこまかき端書きたる、その歌三首あり曰く 幸ありて見つるきのふや詩のみ園色なき今を何地にきえむ。 み空高う雲をば人の夢のあとと夢に相見る秋よ夕戸よ。 ここにしも高きみ花を仰ぐ我秋なほ袖は香ぞ驕りなる。 ○ ゆく秋の落葉恋ひてぞ朽つるままあはただしうも追ひし門出や 乱れてぞみ胸そめてぞ姫紫苑秋むらさきの濃きめし玉へ。 (せつ子さまへかへし。) 十一月七日 快晴 朝、鉄幹氏への手紙投函す。 神田錦町に金子君を訪ふ、路すがら野村兄に立ちよる。 オゝ繁華なる都府よ、人の多くはこの実相の活動に眩惑せられて成心なき一ケの形骸となり了る。吾はこの憐むべき幾多の友を見たり。 悪臭ある風塵を捲いて市街の至る所に吹き廻る、その吹き行く所、吹きつくる所、白粉化せられたる東京てふ者骸骨を連ねて燦として峙つを見る。人は東京に行けば堕落すと云ふ。然り成心なき徒の飄忽としてこの大都塵頭に立つや、先づ目に入る者は美しき街路、電燈、看板、馬車、艶装せる婦人也、胸に標置する所なき者にしてよく此間に立つて毫末も心を動かさざる者あらんや。ああ東京は遊ぶにも都合のよき所勉むるにも都合のよき所なり。 然れども吾人の見る所を以てすれば都府には一の重大なる精神あり。その嚮ふ所は本源の活動にありてよく諸地方の活動に根本の制裁を与ふ。彼が物質上に思想上に常に偉大なる勢力をたもちて全国に命令する体度に至つてよく吾人の渇仰に値することあるべし。都府に於ける人の成功と否とは実にかかる者と自己の胸中の成心との交渉の如何に存す。かの年若き人の奮然と都に入りて自己の立身の道を立てんとするやよし、然れどもその多く志をえずして老いゆく年を死の床に近かしむる者は実にこの一貫せる都府根本の精神を看過してみだりに実相の活動に身を投じ塵烟の猛火にまかれ粉装の渦乱に悩殺せられて遂に自己の存在をすら忘却するに至れば也。ああ吾友の多くはかくてその一生の路を破壊し了れり、我は街頭に立つて現に幾多のかかる髑髏を見たり。 日本力行会にて飯岡三郎君に逢ふ。 金子兄と共に上野公園に紫玉会油絵展覧会を見る。数百枚のうち大方は玉置照信氏一人の作にして吾らの心を満足せしむること少きは残念なりき。数多のうち四枚の裸体画は下谷警察の厳諭によりて取りはづせる由誠に日本は滑稽なりと思ひぬ。 概して色彩の使ひ方如何はしく旧派に属す。「ながめ」玉置もと子作、少女(ヴアイオリンの)照信氏作「新光」照信氏、「怒涛」照信氏、 等やや見るべし。 十一月八日 快晴、 きのふかひ求め来し絵葉書に認めて残紅兄花郷兄箕人兄藻外君に送る。 午後宮永佐吉君大里てふ人と突然来訪せらる。眼は悪しき光を放ち風容自ら野卑也、その昔の機敏の面かげのみ狡猾の相にのこれるが如し。ああこの人この年の三月幼年校を放校せられて以来京に入り種々なる転化の未遂にかかる浅ましくなれる也。我は常にくり返す、日く京は学ぶにも遊ぶにも都合のよき処也と。 郷の田鎖徹郎君端書して阿部君の肋膜炎にかかり岩手病院に入れるを報じ来る。写真を取り出てその凛々しき面影を見想ひは想ひを駆りて吾は遂にはかなくも懐郷の念にうたれぬ。 この夜阿部兄にあてたる長き長き手紙認む。 せつ子君の美しきみ玉章来る、表紙には百合子と認められたるも先づ心ゆく想出也。 かくて我はまた強き思郷の翼にぞかられぬる わかれてよりの長き長き思ひ。いとしき美の筆に上りて、吾にはたとしへもなき尊さの絵巻物なり。胸に溢るめる感懐、ああ吾恋しの白百合の一花よ。 そらなる秋のみ神は夜の黒髪に弦なるお櫛して旅なるこの愁ひ子にささやき玉ひぬ。しろがねのゑまいさはやかなるに我らが恋の祝福をやさとし玉ふ。吾は限りなき想ひもて吾胸なる百合の花をなつかしみぬ。 何なればかくぞ独りほほゑましむるぞ。ああいとしき者ぞ世に尊とかりや。美しの人は云ふ、吾望みのすべては君なりと。ああ吾らは幸ひなる哉。 夜深ふして目白台の森地洩るる燈の光もあはし。想のみ走らせて北なる星にさめぬるとこしえの瞳に、吾は落ちゆく弦月の影を拝したり。 絵葉書二枚その白百合の君に「乱れてぞ」の歌しるして。他の二枚は小野兄小沢兄伊東兄にとて認めたり。 就寝二時。 十一月九日 快晴 朝。髪をととのへ、散歩してかへれるに金子兄、飯岡兄待たれつつあり。 憐みの瞳をもて吾見つる飯岡兄よ、卿が嘗而なしたる罪はたとへ如何に重くとも、悔悟したる今の君に対してああ吾如何でか悪しみの心を胸に秘むるをえんや。君が死せむとせし心根と悔ひて新らしき人とならんとせし覚悟とは君にとりて生涯の最も尊むべき者也。吾は只切に卿の新らしき人として過古の罪を忘れんことを切望す。 悪むべきは社会なる哉、成心なき青年をして邪路に迷はしむるも汝なり。才なき者をしてはからざる人の罪に服せしむるも汝也。吾はこれをまのあたり飯岡君に見る。姦淫の罪の大なるはその人の心霊を無視したれば也。されどあらゆる人の心霊を没却せんとつとむる社会の罪の更に大なるをば世の人はひたすらに看取する勿らんとす。罪悪とは自ら造る者に非ずして社会が作らしむる者也。 されどその責は社会のみに非ず。品性の卑しき当事者も亦あづかつて責あり。 昼食してわかる。 今日は愈々そのまちし新詩社小集の日也。 一時夏村兄と携へて会場に至れば、鉄幹氏を初め諸氏、すでにあり。(牛込神楽丁二丁目二十二、城北倶楽部、) 東京社友間に回覧雑誌編輯の事、 明年一月後の明星体裁変ゆる事、 新派歌集の事、 文芸拡張の主旨にて各地に遊説する事、 新年大会の事、 等を討議す。 集れるは鉄幹氏をはじめ平木白星氏、山本露葉氏、岩野泡鳴氏、前田林外氏、相馬御風君、前田香村君、高村砕雨君、平塚紫袖君、川上桜翠君、細越夏村君、外二名と余と都合十四名也。雑誌は相馬君川上君前田翠渓(欠)君等にて編輯することとなり。その他の件もそれぞれ決したり。新年大会には社友の演劇をも催すべくその脚本は平木氏作る筈也。閑談つきずして興趣こまやかなる一座、就中、平木氏の洒清として親しむべき前田氏の老人の如き風容してよく洒落る、山本氏の丈夫の如き不動の体度等面白し、鉄幹氏は想へるよりも優しくして誰とも親しむ如し。相馬氏の風貌想ひしよりは壮重ならず、平塚氏のみは厭味也。 平木氏は日本国家の作者とも見えぬ清高の趣をもたる人、まことに詩人らしき詩人也。 七時散会。吾は惟ふ。人が我心をはなれて互に詩腸をかたむけて歓語する時、集りの最も聖なる者也と。 都は国中活動力の中心なる故万事活発々地の趣あり。かの文芸の士の、一室に閑居して筆を弄し閑隠三昧に独り楽しめる時代はすでに去りて、如何なる者も社会の一員として大なる奮闘を経ざるべからずなれり。人の値は、大なる戦ひに雄々しく勝ちもしくは雄々しく敗くる時に定まる。 我は今日の集会に人々の進取の気盛んなるに大によろこぶ、その社員遊説の拳の如き以て徴すべし。 ああ吾も亦この後少しく振るふ処あらんか。 小集のかへり相馬御風兄と夏村兄と三人巷街に袖をつらねて散歩す。 九時まで夏村兄と或は小日向台の月色に清吟し或はその詩室に閑話す。 かへりて信書を認めんとし心つかれてならず早く寝に就く。 十一月十日 快晴、 午前。筆を取りて気早く倦み、台に上りて独り漂渺として想ひの宮に憧る。 東都の詞友を想ひ、故山の芳友を思ひ、更に天地大の佳契を懐ふ。昨夜はここに登りて全都の霧衣袖重たげに這ふて、秋皎の月に眠るを見、今、露はれたる満街の雑踏を望みて心平らかならず、遠く北天蒼溟のかなたを仰いで、老榎の下に杖を立つる時、紅袴の少婦袂をあげて吾傍らに走る。 昼食を了へ、早忽として廬を出でて澁谷の諸堂を訪はんとて出づ。 女子大学の前より目白ステーシヨンに至り直ちに乗車して渋谷に到る、里路の屈曲多きを辿ることやや暫らく青桐の籬に沿ふて西に上り詩堂に入る。 先づ晶子女史の清高なる気品に接し座にまつこと少許にして鉄幹氏莞爾として入り来る、八畳の一室秋清うして庭の紅白の菊輪大なるが今をさかりと咲き競ひつつあり。 談は昨日の小集より起りて漸く興に入り、感趣湧くが如し。かく対する時われは決して氏の世に容れられざる理なきを思へり。 氏曰く、文芸の士はその文や詩をうりて食するはいさぎよき事に非ず、由来詩は理想界の事也直ちに現実界の材領たるべからずと。又云ふ、和歌も一詩形には相異なけれども今後の詩人はよろしく新体詩上の新開拓をなさざるべからずと。又云ふ、人は大なるたたかひに逢ひて百方面の煩雑なる事条に通じ雄々しく勝ち雄々しく敗けて後初めて値ある詩人たるべし、と。又云ふ、君の歌は奔放にすぐと。又云ふ、日本の詩人は虚名をうらんとするが故にその名の一度上るや再び落ちんことを恐れて又作らず。我らが友に於て皆然り、と。又曰く、古来日本の詩に最も不完全なりしは比喩の一面にあり、泣菫氏の如きは今までの詩界に最も多く比喩を用ゆる人也と。又云ふ、白星林外諸氏に交はれ。と。 面晤することわづかに二回、吾は未だその人物を批評すべくもあらずと雖ども、世人の云ふことの氏にとりて最も当れるは、機敏にして強き活動力を有せることなるべし。他の凶徳に至りては余は直ちにその誤解なるべきを断ずるをうべし。 晶子女史にとりても然り、而して若し氏を見て、その面貌を云々するが如きは吾人の友に非ず。吾の見るすべてはその凡人の近くべからざる気品の神韻にあり。この日産後漸く十日、顔色蒼白にして一層その感を深うせしめぬ。 鉄幹氏の人と対して城壁を設けざるは一面尚旧知の如し。 四時また汽車にてかへる。弦月美しく夕の空に高う輝き秋声幽にして天外雲空し。 草堂に入れる頃は月色朧ろに目白の森地をてらして、我と自らしらぬ活動のちから胸にみちたる心地せり。残紅兄より手紙と嘗而二人にて写したる写真と来り、菫舟兄より原兄大阪へ出発の報知来る。 嘗而杜陵の秋を人はかなげの夕やとののしりて共に逢魔が時の友の世寒きを自ら高うせしその残紅兄よ。運命のつばさの恐ろしううらめしきは今更ならねど、希くは心して想ひ玉へ。文芸の趣味の人に緊要なるは今更ならねど、さりとて必しも作家のみが文学家にもあるまじ。人は心のもち様にては如何なる職にありても、自らの好尚を満足せしめうる事なるを、ああ友よ静かに想ひ玉へ。 自らひがみたりと云ふ君よ、誰か冷たき世の波に逢ひては運命の路てふ渚辺に枯藻のあぢきなきをしらざらんや。自ら高うし玉へ、かくてぞ大なる値の前にほほえむ日もありなん。賜はりしそのみ歌。 現なり夢ぞとのみのかくながら老いん若きが歌に吊へ。 天地の光そこにを心あてにいつまでかくの暗のまどひぞ。 ああ君よ、まこと、いつまでかくの暗のまどひぞ。星みませ、空仰ぎ玉へ。ああかの大なる光のおたけびの高う高う大なる黙示を与ふるに非ずや。なつかしの友や。 十時ならずして寝に就く。 ○ 想ひのせて想ひに胸の魂ひめて世の海こぐか詩歌の小舟。 小百合ぞと袂に掩ふて一花ははなたざるべき世とも思ひし。 立ち出でてかへり見たりし人の世の高きさとしの渋谷の入日。 たたかひは人に尊き運命なる香るべくして白菊ぞ夢。 若き子の盲目ぞすがる詩のみ袖秋はかなげの手にもゆるさせし。 光なくて(アヤウクモ)辿る渚の夕枯藻よせし運命の大波ぞ世か。 十一月十一日 快晴。 朝、故家より手紙来り北海道なる山本氏よりの送金切手送り来る。 野村兄訪ね来たまひぬ。雑談に時を移し午後一時かへらる。それより外出して日本力行会に金子兄を訪ひ、為替受取て裏神保丁に古本屋尋ねまはり Tales from Shakespeare,By Charles Lamb. Childe Harold,By Byron. Gleanings from the English poets. "Arthur" Tennyson. Seven English classics. 等求め。道を転じて野村兄の自炊を訪ひ夕飯を認め小山芳太郎君に逢ひ夜に入りて清明の月に促されて野村兄と共に散歩にとて出づ。 池の端に至りて漂渺たる夜色に沈々する対岸の燈火まづ吾心をうばひ月色限りもなく愁ひて胸中讃嗟の声低し。ビーヤホールに入りて美しき油絵の下に盃を傾け陶然たる微酔を秋池の清風に弄せられて、上野の山内に入る、月下に屹つ南洲の像を仰ぎて古桜の下を辿り参差する巨樹にたとしへもなき幽懐を起して都らしからざる都の路に微吟す。音楽学校の近くにベンチに倚ればアークの燈光映ゆく寒林の桜樹を描き出し、鳴笛の韻かすかに響き来りぬ。 半弦の月は朗々として天心にかかり北斗蒼瞑として薄霧わづかにただよふ。談たまたま文芸の士となる者を論ずるに至り、友人高談よく気焔揚るに我も亦酔再び熾んなるを覚えぬ。同窓の友と異郷の月にかたる、すでに抑も快なり、況んやその我れに対してよく温情を吐露するに於てをや。眠るが如き月色に歩みて十時かへり、瀬川藻外兄の信書を披見す。懐郷の念、胸をついて起る。ああ親しむべきすべてよ、汝の居る処は故山なり。 友歌あり曰く、(吾にたまひし) 幸かれと祈らじ愛子のもとよりぞ旅路の露に才すてますな。(鶴林光) 三つ葉その一葉は去りぬ光追ふて雲のこなたは秋静か也。(藻外兄) うす暗き黄昏時杜陵城を通りてのみ歌は ここよはたとはの 秋淋しとてのみ歌 流れゆく雲にも長き愁あり月よ下弦の光つめたき。 その夢よ野菊に匂ふ花ならし砕けてここに友ほしき秋。 十一月十二日 快晴、 故山の友への手紙かき初む。 一日英語研究に費す、読みしはラムのセークスピーヤにてロメオエンドジユリエツトなり。 十一月十三日 快晴、 午前英語。 午時より番町なる大橋図書館に行き宏大なる白壁の閲覧室にて、トルストイの我懺悔読み連用求覧券求めて四時かへる。 猪川箕人兄の文杜陵より来る、人間の健康を説き文学宗教を論じ、更に欝然たる友情を展く。げにさなりき、初夏の丑みつ時の寂寥を破りて兄と中津川畔のベンチに道徳を論じニイチエを説きし日もありきよ、その夜の月今も尚輝れり、ああ吾のみ百四十里の南にさすらひて、故友とはなるるこの悲愁!!! まこと今は天の賜ひし貴重なる時也、さなり、思ひのままに勉めんかな。友よさらば安かれ。  Shakespeare's"Coriolanus"求む。 Shakespeare's"Coriolanus"求む。夜ぞふかき空のこなたの旅仮寝さてもかくての夢ならん世か。 落つる葉の身の夕枯やからなりや旅なる窓の小さき袂や。 つみて掩ふてはなたざるべき白百合のみ胸秋なる吾袖めすや。 夕星の瞬き高き雲井より落ちし光と我恋ひむる。 (二首十四日せつ子さまへ) 十一月十四日 午前。 杜陵なる美しの人のもとへながき文認む。 我れ立つて都門の秋風に高歌するに、人は郷に在りて暮袖をやうたはん。高き高き未来の望みに讃ずるにあらずばわれ何ぞかかる悲別の苦しみを自らせんや。されど、我白百合の君、かくてまたん一年二年ぞ夢。の暫らくなれ、大なる楽しみにこの世送らんもすでに眼前に横れる巨虹の如明らかなるならずや。 小沢兄の長文、田鎖石亀両兄の手簡来る。 水心兄! ああ我がユニオン会ぞ如何に、病める阿部兄の枕辺に足下らが談ぜしと云ふ百般の事、若し我郷にあらば共に共に兄らと楽しむべからんを。遊子何すれぞかくは郷信に弱きや。 兄が我らの恋に与へたる同情の深さはやがて我らが兄に対する感謝の深さ也。まこと彼のわかれの一時、万づをこめしかの一眸に、ああ君もそもその心を察したりしか。彼の世の憐むべき誤解者の中によく兄らのみぞ高き同感者てふ我が捧ぐる冠りを戴きうべきならずや。 時は十月の初旬、愁思たえ難くして兄を黒沢尻の郷に訪ひし時兄の情のああ如何許りかこの胸を慰めたりけんよ。九年橋上の月色、朧として兄の面てをてらす時、我れはただひたすらに友の胸のあたたかき血潮をぞ悟りし。吾の紛紜として胸乱るる時先づその情を探りて慰めの匕を投ずる者は友也。友よ尊い哉、兄ら抑も今郷に在りて如何の世をか観ずらん、? 兄らが我ためにせし送別の席上、(ああ思へば心躍るよ)そこに何らの城壁なくしてただただ一道に流淀する天地の和気のみぞ貫きたりし。 人若し、「汝の慰籍者は何ぞ」と問はば余は直ちに答へて示さん、右に白百合の一花を左に郷なるユニオンの友らを指して。 友の校友会雑誌に出すべきてふ「黙」と云ふ文の梗概をききて我はかのバイロンのソリチユード中の精神を思出しぬ―― There is a pleasure in the pathless woods, There is a rapture on the lonely shore, There is society,where none intrudes By the deep sea,and music in its roar; I love not man the less,but nature more, From these our interviews,in which I steal From all I may be,or have been before, To mingle with the Universe,and feel What I can never express,yet can not all conceal. 原兄大阪より端書たまはる。 暮頃夏村さま菫舟様きたる。夏村さまは七時ごろかへらせ玉ひたり。 菫舟兄夜丑三つの頃まで物語らせ玉ひたり。世の中の愛とは何ぞ、はた結婚とは如何、女と云ふ者は如何なる者ぞ、など ああそれ然るか、然り、人は同時に二つを愛する能はずと、此理に於て兄は青年の恋てふ者を却けて曰く、これ妻帯の日に於ける最大なる不幸の源也と。 ああそれ然るか、然らば結婚とは何ぞ、これ従来の社会のそれの如く、単に同棲男女を作るの意なるか? あらず、少くとも吾人の意見を以てすれば心の相結べる男女の更にその体の結同をなす所以の者に外ならず。結婚は実に人間の航路に於ける唯一の連合艦隊也、 されば吾は実に、愛なき結婚を以て不可許の事とし、若しありとすれば人間本然の意義を没却して肉体的野合を遂げたりと云ふを憚らず、何となれば、これたとへ如何の外来の理由ありとするも究竟の見地より見て全く所謂野合に異らざれば也。 さらんからに友の結婚は如何に。兄が初めその否定せるは、たとへ冥々のうちとは云へ二人の間に愛なかりしによれば也。然るを一旦女の信実に感じて之を然定せる所以は実に兄のすでに自ら覚らざる恋心の胸にきざせるによるのみ。 かくて、去る年の十一月九日、天地ほほえみを湛えて兄らが合歓の式を挙げさせ玉ひぬ。多幸なる哉足下。兄がまめやかなる若き妻人のふるまいを見てより今にては甚だ幸なりと云へる者誠にその恋の漸く兄が心に現れ来れる所以のみ、豈他あらんや、豈他あらんや。 吾見たる結婚とは斯くの如き者也。 この夜恰も陰暦十五夜に当る。友かへりて吾一人枳殻の垣根によりて、北の空遙かに眺むとき暗雲たちまち晴れて月朗々天心の祝福をもたらしぬ。ああ美しき人よ、今それ如何の夢をか辿るらんよ。 阿部兄の病めるを想ひ、絵葉書に Byron の Solitude の一節しるして、小沢兄の「黙」てふ論文と対せるを認む。 この日中央会堂に催さるべき唱歌学校生徒の大合奏にて、平木白星氏の「日本国歌」うたふべき由なれど来客のためはたさざりき。 十一月十五日 晴、 細越白螽兄へ久し振りにて手紙認め阿兄への葉書と共に投函し来る。 中西屋より美しき絵葉書求めきたる。かへれば几上にのこしたる菫舟兄、岩動孝久兄の文あり、余が留守中に来られたる由なれど、まこと残り惜しき事したりと思ひ居る折柄、菫舟兄来りて細越夏村兄の許にゆかずやと云ふ、直ちに訪ひしに露子兄も座にありたり。 談は宗教より哲学にわたり中々に花々しかりし。露子兄のは極めて宗教的にして中心自づと動かざる者あるに似たり、子の嘗而ありし日と大に殊なれる驚くべし。野村兄のは普通也、夏村兄に至つては詩海にただよう大方の人のそれと異ならざるべし。 されど思ふ、自らは小にして而して大なりと様に思ふ程滑稽なるはあらじと。これ実に所謂詩人のまぬかれ難き通弊也。大なる者はおのづからにして大なり。偉なる者にして自ら小也と思ふと雖ども、決してその偉なるに差異なき如く、小なる者が大なりと想ふと雖ども決して大とならざる也。 又思ふ、所謂「自然」とは何ぞ、ああ世のあやまれる、吾をして嘔吐を催すに至らしむるか。嗟然。 八時ごろ露子兄の青山にかへるを送りて夏村兄と共に牛門のほとりまで散歩す、十六夜の月初めは鮮かなりしも漸く雲を含み来れり。帰路また夏村兄の室に入りて焼芋に腸ふくらす。 盛中の無名氏よりの端書と、家信金田一花明兄の文を載せたると来る。無名氏とは誰ぞ、何者の悪謔漢がかかる事をするらん、花明氏に至りては、ああ吾友のしたしむ最たる者か。熱涙の筆哀怨の趣をこめて我ために語る。我また報いざるべけんや。今にして吾、出京の途次五城楼下の一夜なかりしを悔ゆ。 然れども遂に詮方なき也。ただそれ報ゆべき者、我蕭々の心をひらくにあるかな。 せつ子の君、阿部兄、小沢兄、へ絵葉書認む。 平木白星氏へも初めての挨拶を絵葉書に認めたり歌一首 世ぞかくと雲に迷はん、はかなげのこの子掩ふべき袖たまはずや。 ○ 運命なりと風にまぎれて秋の花あはただしうも乱れて朽ちし。 相逢ふて霊の響の縦琴にさめてすがりし袖 山こゑて何地追ふべき星の影追ふてはてなき路に立つ身や。 十一月十六日 晴、日曜日 大橋図書館に一日を消す、 帰路、中西屋より Mauriers novel "Trilby" "Selected poems from Wordsworth's" 求む。杜陵より金矢朱絃君の端書きたる。歌あり曰く、 その日君、泣く人みきと日記にあり若きにたえん旅ならばこそ。 十一月十七日 「月」Monthday(ママ) 朝残紅兄より端書が来た。自分は申訳がない程皆さまへ返事もやらんで居る。 午前は読書。午後は日本橋の丸善書店へ行つて、 "Hamlet By Shakespeare" "Longfellow's poem" の Selection とを買つて来た。 若い者が丸善の書籍室に這入つて、つらつら自分の語学の力をはかなむ心の生ずるのは蓋し誰しもの事であらふ。ああ自分も誠に羨ましさに堪えられなかつた。 夜に花郷兄への手紙半分かいた。猪川兄から移転の報知が来た。 平木白星君からも返事の端書が来た、この内に尋ねねばなるまい。 十一月十八日、 午前花郷兄への手紙かいてしまつて、渋民への絵葉書と共に投函した。 午後は図書館に「即興詩人」よむ。飄忽として吾心を襲ふ者、ああ何らの妙筆ぞ。 渋民より夜具来る。お情けの林檎、ああ僕ただ感謝の誠を以て味つた。明星。掛物。足袋。この夜は温かな母君の手になつた蒲団の上に安らかな穏かな夢を恋人の胸にまで走らした。 十一月十九日、 近頃余が日課は殆んど英語のみとなれり。書はロングフエロー、ウヲルズヲルス、トリルビー等也。 この日一日小説の構想と落光記(校友会雑誌へ)の考案にて日をくらす。 人は安閑として居るうちに己れの才を失ふことあり注意せざるべからず。 阿部兄の姉上様より阿部兄の病状よき旨来簡。近来友人の伝ふる所。皆この人の弁舌滔々たるに驚くと。又面白し。 夜遅く、伊東圭一郎兄の手紙と小沢兄の端書と来る。伊兄蘇峯を品?して稍正鵠に近し、彼が業すでに終れり、「結婚論」の近作の如き吾人その浅薄甚しきを認む。 好友等それ吾を想ふ、かくの如き乎。吾はただ多謝す。返書半分かきたれどあまり乱暴故没とす。 この夕、モントゴメリーの詩に「黄昏」 twilight を読む。夕の歌として最上の者也、その宗教詩人たる丈信仰の念躍として紙上に現はる。 ○ 地に伏して朽ちん骸の清き故、思ひ惑ひし夕はなれ雲。 迷ひぞと人のろはしのみ胸せまし、迷ひなるべき人なり世なり。 わだこえてまなこふさぎてみ船追ひてさても何地の岸にすがるべき。(コノ一首抹消) 花や何黄昏雲の淡き身に鐘のろはしの夕蓬原。 かくてただ梢に消えし風の音か花サフランを妬みゆく園。 十一月廿日 友残紅へ二十五枚許りの長手簡認め白羊会雑誌への和歌十首同封す、(午前と夜とにて、)和歌についての事巨細となく云ひやりたり。(投函せず) 午後菫舟兄来訪せらる。夕方かへる。今日は格別のはなしもなかりき。 せつ子様の封緘葉書きたる、友と話しつつある時なりければ秘せんとしてかへつて顔ほとるを覚へぬ。語に曰く、「今おかしき姿して写真致してまゐり候」と。又曰く、外国人より英語習ひ居ると。 我は常に吾等の恋を想ふ毎に、世の人の恋の何故はかなきかを怪しまざるをえず。二つの心霊の相携へ相婚したる時、その価ひ果して世人の見る如く低き者なりや。人は恋よりも却つて結婚を尊べども吾にしてはしからず、真の結婚とは、心と体との両方面に於て初めて成さる者也。而してそは常に、先づ心の相携ふるありて後に体の相抱くのみ。世人の迷へること実に憐れむべき程也。 十一月廿一日 思想紛糾して落袖記成らず。 瀬川藻外兄より端書と、白羊会十一月礼会の詠草と来る。ああ吾誠に御無沙汰して居たり。 夜、中西屋、丸善等をたづね、せつ子様に送るべきネスフイルド グランマーの一、及びウオルズヲースの詩抄、イプセンの散文劇詩 John Gabriel Borkman のオーサー英訳買ひ来る。 絵葉書、せつ子様、小沢兄等へしたたむ。水心兄へは海岸の景色に Longfellowの「潮のみち干」の一節をしるして。 渋民よりみつ子の文きたる。 ―――――――――――――――― 吾は近頃蔵書の多くを英語をのぞいては大抵売り払ひたり。甚だ気持よし。 床の間には余がこの夏嘗つて渋民に居て掛けたる勿来の関の碑の一軸を下げたり。こはかの君きたりし時も白菊の鉢置きたる床にかけし者也。なつかしきは吾に文玉ふ人々とこの掛物、母が手づからせし夜具、と自分の体也。呵々。 妹は今年十五、心稚けれど我を想ひてや文したる心根これもなつかし。 十一月廿二日 土曜日、 午後図書館に行き急に高度の発熱を覚えたれど忍びて読書す。四時かへりたれど悪寒頭痛たへ難き故六時就寝したり。折悪く坂下の小社の縁日の事とて雑駁の声紛々として耳を聾せしめんとす。かくて妄想ついで到り苦悶のうちに眠れるは九時すぐる頃なりき。終夜たへず種々の夢に侵さる。 「即興詩人」中に世界を美しき乙女にたとへて、世の人はその局所細繊の所のみを詮索すれども、詩人は全体の美しきを観照して吟咏す云々の条あり。以て詩人芸術家一般の批判となすべし。 十一月廿三日 日曜日 朝目覚めて、心地尚平常の如く快からざるを覚えたれどつとめて 一日イプセンの John Gabriel Borkman を訳出す。(十三頁まで) 家信来る。 十一月廿四日 月曜日。 古本屋より、高橋五郎の「英独詩文研鑽」求め来る。 盛岡へ、せつ子様、小沢兄等へ認め置きし絵葉書投函す。妹へも山家の景色の絵葉書出す。 野村兄の端書来る。 夜十一時までに「ボルクマン」読み了る。 十一月廿五日 火曜日、 午前安村省三兄、野村兄来訪せらる。 猪川兄等のことに就いて野村兄より詰らなき「大事」をききたり、二時かへる。 イプセンのボルクマン訳す。 余はこの頃健康の衰へんことを恐る。 十一月廿六日 水曜日 英訳。 午後、中西屋より Mr Punchs pocket Losen By Anstey. Orloff and his wife By Gorky. 買ひ来る。 阿部兄小沢兄へ絵葉書認む。 小沢兄の葉書来る、初雪ふれる由。 十一月廿七日 木曜日 一日英語。 夕方三丁目の後方の芝地にてゴルキイ読む、秋の蝶飛び来れるに興覚えて落日の頃まで草の上に横はる。 十一月廿八日 金曜日 この頃の起床は八時すぎ就寝は十一時すぎ。 イプセン訳述。 一昨日認めたる絵葉書投函す。 珈琲をかひて独り寂しくも草堂に味ふ。 友藻外へ絵葉書認む。 十一月廿九日 土曜日 夜夏村兄訪はれ十時ころまで談話す。 十一月三十日 日、 朝めさむれば、枕頭に匂ふ白百合のみ姿あり、せつ子の君杜陵より新らしき写真たまひぬ。 午砲の頃またその美しきみ文来る。み手づから編ませしてふ美しの枝折、歌さへ添えて。 かくて吾は一日限りなき追想と希望とを胸に描きて喜びのうちに暮しぬ、机上に立てたる小照の星の雫の宿りけんやさ眉の面影に、ああ吾はたとしえもなきこころの靄の中をさ迷ふ心地しぬ。 時の流の末に横はらん香ぐはしの花の床ぞ待たるる哉、幸てふきづなの二の胸結ばん日の憧るる哉。 今日にて吾はこの地にきてより正に三十夜の夢結ばんとす、飄々として遊子孤袖寒し、前途を想ひ恋人を忍びては万感胸に溢れて懐泣の時を重ぬること三時までに及びぬ、ああそれ何地にか天籟の響を風骨にただよはさん者ぞ。 都府とや、ああこれ何の意ぞ。吾関を出でて相交はる髑髏百四十万。惨たる哉、吾友は今、吾胸に満足せしむべくあまりに賢きを如何せん、吃、天地の間、吾道何ぞ茫漠たるや。 あらず、自を信ずる者、大なる思想を仰ぐ者、高き光を目ざす者、何すれぞ、強いて狭き籠の中を慕はんや。恋人は云ふ、理想の国は詩の国にして理想の民は詩人なり、狭き亜細亜の道を越えて立たん曠世の詩才、君ならずして誰が手にかあらんや。妾も君成功の凱旋の日は、成功に驕る手か失敗にわななく指かして祝ひの歌奏でん。と、ああさらばこれ何らの高き幸ぞ、吾恋ふ君よ、永世の恋の囁き、君ならずして何の人かよく吾胸に吹き込みえんや。後の日の聖なる園の曙を、東雲の恋の光眩き程に世の人驚かさんため、ああかくて今暫らくの旅心運命の波に漂はさんか。 吾ははしなくも杜陵の地にかへらんことを祈りぬ二十日の後には夏村兄もかへらんと云ふ。しかはあれああ吾のみは寂しくも異郷の月に年越の袖振らなんか。親しかりし友人よ、兄らのみぞ吾この心知りたまはん。 今訳しつつある「死せる人」(イプセン)は早く脱稿して出版せしめん。「活動」の意義は決して忽せたる者ならず。吾は吾信ずる所に行かんのみ、世の平凡者流の足跡を迫るが如きは、高俊の心ある者の堪えうる所に非ざるなり。 出でて銀河を仰げ、北に走る三千丈の壮姿、猶且つ恋てふ星の涙に非ずや、北斗光閃として不動、吾希望の明りも亦そこにあり。焉。 拾二月 十二月一日、 郷を去つて月一度めぐりぬ。満都風寒し。旅情自らこまやか也。 堀内錬三君より端書来る。 ああ汝故郷よ。岩峯の銀衣、玉東の白袖、夫れ依然として旧態の美あるか。江東嘗而、故郷を論じ「形逝いて神遊ぶ」と云へり。宜なる哉。郷村不断の自然の霊、今尚ほ、清秀の趣を湛えて、初冬の灝気、朴直の農人の胸に呼吸せらるか。吾たえずああ吾堪えず。 この夏、山村水郭の涼しさを恋しき君と共にする三夜。野流潺々として音清き所、豆の葉を踏んで人百合の花を含む。高姿、彷彿として今吾目にあり。ああされど身はこれ遊子相へだつ百四十里なるを如何せん。 嘗而従兄と山野に猟す。雪鞋氷を踏んで寒林に佳禽をさぐる。往く往く山深うして自然の形神威あり。徐ろに故郷の山川を眺望して精気脈管に迸り出るを覚えき。野鶏足下の叢を出でて飛ぶ。高翔の摧羽響、尚耳にあり。ああされど吾は巷街の塵に歩むを如何せん。 感調胸に溢れてこの夜おそく恋しき人への文半ばしたたむ。几上の写真をみては、心何とはしらず春のたたずまいす。 地に下りて秋の霜ふむ蝶や身やかくて寒さのたえ難き世や。 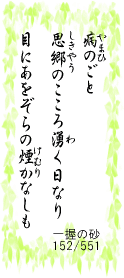 十二月二日 午前恋しき君への文かき了へて投函す。 田村の姉方より杜陵の端書きたる、転居せる趣しるしたり。 十二月三日 イプセン集ひもとく。 午後一人散歩す。 十二月十九日 夜。 日記の筆を断つこと茲に十六日、その間殆んど回顧の涙と俗事の繁忙とにてすぐしたり。 ※明治三十五年秋韷笛語終り。 この後、石川啄木は病気に罹り、翌年2月、迎えに来た父親とともに帰郷し、療養します。 明治三十七年一月一日からの日記「甲辰詩程」が遺されています。 明治35年12月20日~明治36年12月末までの日記は遺されていません。 ページトップ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
石川啄木 啄木日記 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
