 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(題字は石川啄木「悲しき玩具」直筆ノートより、写真は啄木が過ごした現在の小樽と小樽水天宮境内の歌碑) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
明治四十二年日誌 石川啄木 啄木日記 石川啄木 啄木日記の原本は、次のものを使用しています。 発行所:株式会社岩波書店 書 名:啄木全集 全17冊のうち、第15集 発行日:昭和36年10月10日 新装第1刷 なお、筑摩書房版全集と照合し、不突合の場合は調査、不明の場合は筑摩版を採用しました。 原文で使用している仮名遣いや送り仮名は極力原文どおりとしていますが、漢字はウェブ表示上問題があると思われる文字については、現在使われている文字またはかなに置き換えていますのでご了承ください。 NIKKI Ⅰ MEIDI 42 NEN ―― ○ ―― 1909 APRIL TOKYO 7TH,WEDNESDAY, HONGO-KU MORIKAWA-TYO 1 BANTI, SIN- SAKA359GO,GAIHEI-KAN-BESSO NITE Hareta Sora ni susamajii Oto wo tatete,hagesii Nisikaze ga huki areta. ※ローマ字日記はこんなふうに始まるのですが、以下、日本語で表示します。 かな・漢字は上記全集に沿っていますが、一部変更しています。 日記 Ⅰ 明治四十二年 ―― ○ ―― 1909 4月 七日 水曜日 本郷区森川町一番地新坂 359号蓋平館別荘にて 晴れた空にすさまじい音をたてて、激しい西風が吹き荒れた。三階の窓という窓は絶え間もなくガタガタ鳴る。その隙間からは、はるか下から立ち昇った砂ほこりがサラサラと吹き込む。そのくせ、空に散らばった白い雲はちっとも動かぬ。午後になって風はようよう落ちついた。 春らしい日影が窓の磨りガラスを暖かに染めて、風さえなくば、汗でも流れそうな日であった。いつも来る貸本屋のおやじ、手のひらで鼻をこすりあげながら、「ひどく吹きますなあ、」と言って入って来た。 「ですが今日中にゃ東京中の桜が残らず咲きますぜ、風があったって、あなた、この天気でございますもの。」 「とうとう春になっちゃったねえ!」と予は言った。無論この感慨はおやじにはわかりっこない。「エー!! エー!!」とおやじは答えた。「春はあなた、私どもには禁物でございますね、貸本は、もう、からだめでがす。本なんか読むよりゃ、まだ遊んで歩いた方がようがすから、無理もないんですが、読んで下さる方も自然とこう長くばかりなりますんでね。」 昨日社から 仕様ことなしに、ローマ字の表などを作ってみた。表の中から、時々、津軽の海の彼方にいる母や妻のことが浮かんで予の心をかすめた。「春が来た、四月になった。春! 春! 花も咲く! 東京へ来てもう一年だ!……が、予はまだ予の家族を呼びよせて養う準備ができぬ!」近ごろ、日に何回となく、予の心の中をあちらへ行き、こちらへ行きしてる問題はこれだ…… そんならなぜこの日記をローマ字で書くことにしたか? なぜだ? 予は妻を愛してる。愛してるからこそこの日記を読ませたくないのだ、―しかしこれはうそだ! 愛してるのも事実、読ませたくないのも事実だが、この二つは必ずしも関係していない。 そんなら予は弱者か? 否、つまりこれは夫婦関係という間違った制度があるために起こるのだ。夫婦! 何という馬鹿な制度だろう! そんならどうすればよいか? 悲しいことだ! 札幌の橘智恵子さんから、病気がなおって先月二十六日に退院したというハガキが来た。 今日はとなりの部屋へ来ている京都大学のテニスの選手等の最後の決戦日だ。みんな勇ましく出て行った。 昼飯を食っていつものごとく電車で社に出た。出て、広い編集局の片隅でおじいさんたちと一緒に校正をやって、夕方五時半頃、第一版が校了になると帰る。これが予の生活のための日課だ。 今日、おじいさんたちは心中の話をした。何という鋭いアイロニイだろう! また、足が冷えて困る話をして、「石川君は、年寄りどもが何を言うやらと思うでしょうね、」と、卑しい、助平らしい顔の木村じいさんが言った。「ハ、ハ、ハ、…、」と予は笑った。これも又立派なアイロニイだ! 帰りに、少し買物をするため、本郷の通りを歩いた。大学構内の桜は、今日一日に半分ほど開いてしまった。世の中はもうすっかり春だ。行き来の人の群がった巷の足音は何とはなく心を浮き立たせる。どこから急に出て来たかと怪しまれるばかり、美しい着物を着た美しい人がゾロゾロと行く。春だ! そう予は思った。そして、妻のこと、可愛い京子のことを思い浮かべた。四月までにきっと呼び寄せる、そう予は言っていた。そして呼ばなかった、否、呼びかねた。 おお、予の文学は予の敵だ、そして予の哲学は予のみずからあざける論理に過ぎぬ! 予の欲するものは沢山あるようだ。しかし、実際はほんの少しではあるまいか? 金だ! 隣室の選手どもはとうとう東京方に負けたらしい。八時頃、金田一君と共に通りに新しく建った活動写真を見に行った。説明をする男はいずれもまずい。そのうちに一人、 十時過ぎ、帰って来ると、隣室は大騒ぎだ。慰労会に行って酔っぱらってきた選手の一人が、電灯をたたきこわし、障子の 寝静まった都の中に一人目覚めて、おだやかな春の夜の息を数えていると、三畳半の狭い部屋の中の予の生活は、いかにも味気なく、つまらなく感ぜられる。この狭い部屋の中に、何とも知れぬ疲れにただ一人眠っている姿はどんなであろう。人間の最後の発見は、人間それ自身がちっとも偉くなかったということだ! 予はこのけだるい不安と 枕の上で、『ツルゲーネフ短編集』を読む。 八日 木曜日 多分、隣室の忙しさに紛れて忘れたのであろう、(忘られるというのがすでに侮辱だ。今の予の境遇ではその侮辱が、また当然なのだ。そう思って予はいかなることにも笑っている。)起きて顔を洗ってきてから、二時間たっても朝飯の膳を持ってこなかった。 予は考えた。予は今迄こんな場合には、いつでも黙って笑っていた。ついぞ 空はおだやかに晴れた。花時の巷は何となく浮き立っている。風が時々砂を捲いてそぞろ行く人々の花見衣をひるがえした。 社の帰り、工学士の日野沢君と電車で一緒になった。チャキチャキのハイカラッ児だ。その仕立おろしの洋服姿と、袖口の切れた綿入れを着た予と並んで腰をかけたときは、すなわち予の口から何か皮肉な言葉の出ねばならぬ時であった。「どうです、花見に行きましたか?」「いいえ、花見なんかする暇がないんです。」「そうですか、それは結構ですね、」と予は言った。予の言ったことは、すこぶる平凡なことだ。誰でも言うことだ。そうだ、その平凡なことをこの平凡な人に言ったのが、予は立派なアイロニイのつもりなのだ。無論日野沢君にこの意味のわかる気遣いはない。一向平気なものだ。そこが面白いのだ。 予らと向かい合って、二人のおばあさんが腰かけていた。「僕は東京のおばあさんが嫌いですね、」と予は言った。「なぜです?」「見ると感じが悪いんです。どうも気持ちが悪い。田舎のおばあさんのように、おばあさんらしいところがない。」その時、一人のおばあさんは黒眼鏡の中から予を 「そうですか、」と日野沢君はなるべく小さい声で言った。 「もっとも同じ女でも若いのなら東京に限ります。おばあさんときちゃ、みんな小憎らしい 「ハ、ハ、ハ、ハ。」 「僕は活動写真が好きですよ。君は?」 「まだわざわざ見に行ったことはありません。」 「面白いもんですよ。行ってごらんなさい。何でしょう、こう、パーッと明るくなったり、パーッと暗くなったりするんでしょう? それが面白いんです。」 「眼が悪くなりますね、」と言うこの友人の顔には、きまり悪い当惑の色が明らかに読まれた。予はかすかな勝利を感ぜずにはいられなかった。 「ハ、ハ、ハ!」と、今度は予が笑った。 着物の裂けたのを縫おうと思って、夜八時頃、針と糸を買いに一人出かけた。本郷の通りは春の賑わいを見せていた。いつもの夜店のほかに、植木屋が沢山出ていた。人はいずれも楽しそうに肩と肩を摩って歩いていた。予は針と糸を買わずに、「やめろ、やめろ」と言う心の叫びを聞きながら、とうとう財布を出してこの帳面と 菫の鉢の一つを持って金田一君の部屋に行った。「昨日あなたの部屋に行った時、言おう言おうと思ってとうとう言いかねたことがありました、」と友が言った。面白い話が斯くて始まったのだ。 「何です? ……さあ、一向分からない!」 友は幾たびかためらった後、ようよう言い出した。それはこうだ――。 京都の大学生が十何人、この下宿に来て、七番と八番、即ち予と金田一君との間の部屋に泊ったのは、今月のついたちのことだ。女中はみな大騒ぎしてその方の用にばかり気を取られていた。中にもおきよ――五人のうちでは一番美人のおきよは、ちょうど三階持ちの番だったもんだから、ほとんど朝から晩――夜中までもかの若い元気のある学生どもの中にばかりいた。みんなは「おきよさん、おきよさん!」と言って騒いだ。中にはずいぶんいかがわしい言葉や、くすぐるような気配なども聞えた。予はしかし、女中どもの挙動にチラチラ見える虐待には慣れっこになっているので、したがって彼らのことには多少無関心な態度を取れるようになっていたから、それに対して格別不愉快にも感じていなかった。しかし、金田一君は、その隣室の物音の聞こえるたび、言うに言われぬ嫉妬の情にかられたという。 嫉妬! 何という微妙な言葉だろう! 友はそれを抑えかねて、果ては自分自身を浅ましい嫉妬深い男と思い、ついたちから四日までの休みを全く不愉快に送ったという。そして五日の日に三省堂へ出て、ホッと安心して息をつき、小詩人君(その編集局にいる哀れな男)の言い草ではないが、家にいるよりここの方がいくら気がのんびりしてるだろうと思った。それからようやく少し平常の気持ちになり得たとのことだ。 おきよというのは二月の末に来た女だ。肉感的に肥って、血色がよく、眉が濃く、やや角張った顔に太いきかん気が表れている。年は二十だという。何でも、最初来た時金田一君にだいぶ接近しようとしたらしい。それをおつね――これも面白い女だ――がむきになって妨げたらしい。そして、おきよは急にわが友に対する態度を改めたらしい。これは友の言うところでほぼ察することができる。友はその後、おきよに対して、ちょうど自分の家へ飛んで入った小鳥に逃げられたような気持ちで、絶えず眼をつけていたらしい。おきよの生まれながらの挑発的な、そのくせどこか人を圧するような態度はまた、女珍しい友の心をそれとなく支配していたとみえる。そして金田一君――今迄女中に祝儀をやらなかった金田一君は、先月の晦日におきよ一人にだけなにがしかの金をくれた。おきよはそれを下へ行ってみんなに話したらしい。あくる日からおつねの態度は一変したという。まことに馬鹿な、そして憐れむべき話だ。そしてそれこそ真に面白味のあることだ。そこへもってきて大学生がやって来たのだ。 おきよは強い女だ! と二人は話した。五人のうち、一番働くのはこのおきよだ。その代わりふだんには、夜十時にさえなれば、人にかまわず一人寝てしまうそうだ。働きぶりには誰一人及ぶ者がない。従っておきよはいつしかみんなを圧している。ずいぶんきかん気の、めったに泣くことなどのない女らしい。その性格は強者の性格だ。 一方、金田一君が嫉妬ぶかい、弱い人のことはまた争われない。人の性格に二面あるのは疑うべからざる事実だ。友は一面にまことにおとなしい、人の好い、やさしい、思いやりの深い男だと共に、一面、嫉妬ぶかい、弱い、小さなうぬぼれのある、めめしい男だ。 それは、まあ、どうでもよい。その学生どもは今日みんな発ってしまって、たった二人残った。その二人は七番と八番へ、今夜一人づつ寝た。 予は遅くまで起きていた。 ちょうど一時二十分頃だ。一心になってペンを動かしていると、ふと、部屋の外に忍び足の音と、せわしい息遣いとを聞いた。はて! そう思って予は息をひそめて聞き耳をたてた。 外の息遣いは、シンとした夜更けの空気に嵐のように烈しく聞こえた。しばらくは歩く気配がない。部屋部屋の様子を覗っているらしい。 予はしかし、初めからこれを盗人などとは思わなかった。……! 確かにそうだ! ツと、大きく島田を結った女の影法師が入り口の障子に鮮やかに映った。―― ――! 強い女も人に忍んで梯子を上がってきたので、その息遣いの激しさに、いかに心臓が強く波打ってるかがわかる。影法師は廊下の電灯のために映るのだ。 隣室の入り口の廻し戸が静かに開いた。女は中に入って行った。 「ウーウ。」とかすかな声! 寝ている男を起したものらしい。 間もなく女は、いったん閉めた戸を、また少し細目に開けて、予の部屋の様子を覗ってるらしかった。そしてそのまま又中へ行った。ウーウ―ウ。」とまた聞こえる。かすかな話し声! 女はまた入り口まで出て来て戸を閉めて、二三歩歩く気配がしたと思うと、それっきり何の音もしなくなった。 遠くの部屋で「カン」と一時半の時計の音。 かすかに鶏の声。 予は息がつまるように感じた。隣室では無論もう予も寝たものと思ってるに違いない。もし起きてる気配をさしたら、二人はどんなにか困るだろう。こいつあ困った。そこで予はなるたけ音のしないように、まず羽織を脱ぎ、足袋を脱ぎ、そろそろ起き上がってみたが、床の中に入るにはだいぶ困難した。とにかく十分ばかりもかかって、やっと音なく寝ることができた。それでもまだ何となく息がつまるようだ。実にとんだ目に遭ったものだ。 (※省略) なぜか予はさっぱり心を動かさなかった。予は初めからいい小説の材料でも見つけたような気がしていた。 「一体なんという男だろう? きっと―― ――手に入れたいばっかりに、わざわざ居残ったものだろう。それにしても、―― ――奴、ずいぶん大胆な女だ。」こんなことを考えた。「明日早速―― ―――― ――ようか? いや、―― ――のは残酷だ……いや、―― ――方が面白い……」二時の時計が鳴った。 間もなく、予は眠ってしまった。 九日 金曜日 桜は九分の咲き。暖かな、おだやかな全く春らしい日で、空は遠く花曇りにかすんだ。 おととい来た時は何とも思わなかった智恵子さんのハガキを見ていると、なぜかたまらないほど恋しくなってきた。「人の妻にならぬ前に、たった一度でいいから会いたい!」そう思った。 智恵子さん! なんといい名前だろう! あのしとやかな、そして軽やかな、いかにも若い女らしい歩きぶり! さわやかな声! 二人の話をしたのはたった二度だ。一度は大竹校長の家で、予が解職願いを持って行った時。一度は ああ! 別れてからもう二十ヶ月になる! 昨夜のことを金田一君に話してしまった。無論そのために友の心に起こった低気圧は一日や二日で消えまい。今日一日何だか元気がなかった。といって、友は別におきよに恋してるわけでは無論ない。が、予のようにこのことを面白がりはしなかったのは事実だ。男は若園という奴なことはすぐ知れた。彼は夜九時頃になって発って行った。おきよとの別れの言葉は金田一君と共にこの部屋にいて聞いた。その模様では、何でも渡辺という姓の男との張り合いから、一人残って―― ――手に入れる決心をしたものらしい。男の発った後、女はすぐ鼻唄を歌いながら立ち働いていた。 社では今日第一版が早く済んで、五時頃に帰って来た。 夜、出たくてたまらぬのを無理におさえてみた。 帰りの電車の中で、去年の春別れたまま会わぬ京子によく似た子供を見た。ゴムダマの笛を「ピーイ」と鳴らしては予の方を見て、恥ずかしげに笑って顔を隠し隠しした。予は抱いてやりたいほど可愛く思った。 その子の母な人は、また、その顔の形が、予の老いたる母の若かった頃はたぶんこんなだったろうと思われるほど鼻、頬、眼……顔一体が似ていた。そして、あまり上品な顔ではなかった! 乳のように甘い春の夜だ! 釧路の小奴――坪仁子からなつかしい手紙がきた。 遠くで 枕の上で今月の「中央公論」の小説を読む。 十日 土曜日 昨夜は三時過ぎまで床の中で読書したので、今日は十時過ぎに起きた。晴れた空を南風が吹きまわっている。 近頃の短篇小説が一種の新しい写生文に過ぎぬようなものとなってしまったのは、否、我々が読んでもそうとしか思わなくなってきた――つまり不満足に思うのは、人生観としての自然主義哲学の権威がだんだん無くなってきたことを示すものだ。 時代の推し移りだ! 自然主義は初め我らの最も熱心に求めた哲学であったことは争われない。が、いつしか我らはその理論上の矛盾を見出した。そしてその矛盾を突っ越して我らの進んだ時、我らの手にある剣は自然主義の剣ではなくなっていた。――少なくも予一人は、もはや傍観的態度なるものに満足することができなくなってきた。作家の人生に対する態度は、傍観ではいけぬ。作家は批評家でなければならぬ。でなければ、人生の改革者でなければならぬ。また……… 予の到達した積極的自然主義は即ちまた新理想主義である。理想という言葉を我らは長い間侮辱してきた。実際また嘗て我らの抱いていたような理想は、我らの発見したごとく、哀れな空想に過ぎなかった。「ライフ・イリュージョン」に過ぎなかった。しかし、我らは生きている。また、生きねばならぬ。あらゆるものを破壊しつくして新たに我らの手ずから樹てたこの理想は、もはや哀れな空想ではない。理想そのものはやはり「ライフ・イリュージョン」だとしても、それなしには生きられぬのだ!――この深い内部の要求までも捨てるとすれば、予には死ぬよりほかの道がない。 ―――――――――――――――――― 今朝書いておいたことは嘘だ、少なくとも予にとっての第一義ではない。いかなることにしろ、予は、人間の事業というものを偉いものと思わぬ。ほかのことより文学を偉い、尊いと思っていたのはまだ偉いとはどんな事か知らぬ時のことであった。人間のすることで何一つ偉いことがあり得るものか。人間そのものがすでに偉くも尊くもないのだ。 予はただ安心をしたいのだ! ――こう、今夜初めて気がついた。そうだ、全くそうだ。それに違いない! ああ! 安心――何の不安もないという心持は、どんな味のするものだったろう! 長いこと――物心ついて以来、予はそれを忘れてきた。 近頃、予の心の最ものんきなのは、社の往復の電車の中ばかりだ。家にいると、ただ、もう、何のことはなく、何かしなければならぬような気がする。「何か」とは困ったものだ。読むことか? 書くことか? どちらでもないらしい。否、読むことも書くことも、その「何か」のうちの一部分にしか過ぎぬようだ。読む、書く、というほかに、何の私のすることがあるか? それは分からぬ。が、とにかく何かをしなければならぬような気がして、どんなのんきなことを考えている時でも、しょっちゅう後ろから「何か」に追っかけられているような気持ちだ。それでいて、何にも手につかぬ。 社にいると、早く時間が経てばよいと思っている。それが、別に仕事がいやなのでもなく、あたりのことが不愉快なためでもない。早く帰って「何か」しなければならぬような気に追ったてられているのだ。何をすればよいのか分からぬが、とにかく「何かしなければならぬ」という気に、後ろから追ったてられているのだ。 風物の移り変わりが鋭く感じられる。花を見ると、「あー花が咲いた」ということ――その単純なことが矢のように鋭く感じられる。それがまたみるみる開いてゆくようで、見てるうちに散るときが来そうに思われる。何を見ても、何を聞いても、予の心はまるで急流に臨んでいるようで、ちっとも静かでない、落ち着いていない。後ろから押されるのか、前から引っ張られるのか、何にしろ予の心は静かに立っていられない、駆け出さねばならぬような気持ちだ。 そんなら予の求めているものは何だろう? 名? でもない、事業? でもない、恋? でもない、知識? でもない。そんなら金? 金もそうだ。しかしそれは目的ではなくて手段だ。予の心の底から求めているものは、安心だ、きっとそうだ! つまり疲れたのだろう! 去年の暮れから予の心に起こった一種の革命は、非常な勢いで進行した。予はこの百日の間を、これという敵は眼の前にいなかったにかかわらず、常に武装して過ごした。誰彼の区別なく、人は皆敵にみえた。予は、一番親しい人から順々に、知ってる限りの人を残らず殺してしまいたく思ったこともあった。親しければ親しいだけ、その人が憎かった。「すべて新しく、」それが予の一日一日を支配した「新しい」希望であった。予の「新しい世界」は、即ち、「強者――『強きもの』――の世界」であった。 哲学としての自然主義は、その時「消極的」の本丸を捨てて、「積極的」の広い野原へ突貫した。彼――「強きもの」は、あらゆる束縛と因襲の古い鎧を脱ぎ捨てて、赤裸々で、人の力を借りることなく、勇敢に戦わねばならなかった。鉄のごとき心を以て、泣かず、笑わず、何の顧慮するところなく、ただましぐらに、己の欲するところに進まねばならなかった。人間の美徳といわれるあらゆるものを塵のごとく捨てて、そして、人間のなし得ない事を平気でなさねばならなかった、何のために? それは彼にも分らない。否、彼自身が彼の目的で、そしてまた人間全体の目的であった。 武装した百日は、ただ武者ぶるいをしてる間に過ぎた。予は誰に勝ったか? 予はどれだけ強くなったか? ああ! つまり疲れたのだ。戦わずして疲れたのだ。 世の中を渡る道が二つある。ただ二つある。「オール オア ナッシング!」一つは凡てに対して戦うことだ。これは勝つ、しからずんば死ぬ。も一つは何ものに対しても戦わぬことだ。これは勝たぬ。しかし負けることがない。負けることのないものには安心がある。常に勝つものには元気がある。そしてどちらも物に恐れるということがない……そう考えても心はちっとも晴れ晴れしくも元気よくもならぬ。予は悲しい。予の性格は不幸な性格だ。予は弱者だ、誰のにも劣らぬ立派な刀を持った弱者だ。戦わずにはおられぬ、しかし勝つことはできぬ。しからば死ぬほかに道はない。しかし死ぬのはいやだ。死にたくない! しからばどうして生きる? 何も知らずに農夫のように生きたい。予はあまり賢すぎた。発狂する人がうらやましい。予はあまりに身も心も健康だ。ああ、ああ、何もかも、すべてを忘れてしまいたい! どうして? 人のいない所へ行きたいという希望が、このごろ、時々予の心をそそのかす。人のいない所、少なくとも、人の声の聞えず、否、予に少しでも関係のあるようなことの聞えず、誰も来て予を見る気遣いのない所に、一週間なり十日間なり、否、一日でも半日でもいい、たった一人ころがっていてみたい。どんな顔をしていようと、どんななりをしていようと、人に見られる気遣いのない所に、自分の身体を自分の思うままに休めてみたい。 予はこの考えを忘れんがために、時々人の沢山いる所――活動写真へ行く。また、その反対に、何となく人――若い女のなつかしくなった時も行く。しかしそこにも満足は見出されない。写真――ことにも最も馬鹿げた子供らしい写真を見ている時だけは、なるほど強いて子供の心に返って、すべてを忘れることもできる。が、いったん写真がやんで「パーッ」と明るくなり、数しれぬウヨウヨした人が見え出すと、もっとにぎやかな、もっと面白い所を求める心が一層強く予の胸に湧き上がってくる。時としては、すぐ鼻の先に強い髪の香を嗅ぐ時もあり、暖かい手を握っている時もある。しかしその時は予の心が財布の中の勘定をしている時だ。否、いかにして誰から金を借りようかと考えている時だ! 暖かい手を握り、強い髪の香を嗅ぐと、ただ手を握るばかりでなく、柔らかな、暖かな、真っ白な身体を抱きたくなる。それを遂げずに帰って来る時の寂しい心持ち! ただに性欲の満足を得られなかったばかりの寂しさではない。自分の欲するものはすべて得ることができぬという深い、恐ろしい失望だ。 (※中間略) すでに人のいない所へ行くことも出来ず、さればといって、何一つ満足を得ることもできぬ。人生そのものの苦痛に耐え得ず、人生そのものをどうすることもできぬ。すべてが束縛だ、そして重い責任がある。どうすればよいのだ? ハムレットは、「To be,or,not to be?」と言った。しかし今の世では、死という問題はハムレットの時代よりももっと複雑になった。ああ、イリア! "Three of them"の中のイリア! イリアの企ては人間の企て得る最大の企てであった! 彼は人生から脱出せんとした、否、脱出した。そしてあらん限りの力を以て、人生――我らのこの人生から限りなき暗黒の道へ駆け出した。そして、石の壁のために頭を粉砕して死んでしまった! ああ! イリアは独身者であった。予はいつでもそう思う。イリアはうらやましくも独身者であった! 悲しきイリアと予との相違はここだ! 予は今疲れている。そして安心を求めている。その安心とはどんなものか? どこにあるのか? 苦痛を知らぬ昔の白い心には百年経っても帰ることができぬ。安心はどこにある? 「病気をしたい。」この希望は永いこと予の頭の中にひそんでいる。病気! 人の厭うこの言葉は、予には故郷の山の名のようになつかしく聞こえる!――ああ、あらゆる責任を解除した自由の生活! 我らがそれを得るの道は、ただ病気あるのみだ! 「みんな死んでくれればいい。」そう思っても誰も死なぬ。「みんなが俺を敵にしてくれればいい。」そう思っても誰も別段敵にもしてくれぬ、友達はみんな俺を憐れんでいる。ああ!なぜ予は人に愛されるのか? なぜ予は人を しかし予は疲れた! 予は弱者だ! 一年ばかりの間、いや、一月でも、 一週間でも、三日でもいい、 神よ、もしあるなら、ああ、神よ 私の願いはこれだけだ、どうか、 身体をどこか少しこわしてくれ、痛くても かまわない、どうか病気さしてくれ! ああ! どうか…… 真っ白な、柔らかな、そして 身体がふうわりとどこまでも―― 安心の谷の底までも沈んでゆくような布団の上に、いや、 養老院の古畳の上でもいい、 なんにも考えずに、(そのまま死んでも 惜しくはない!)ゆっくりと寝てみたい! 手足を誰か来て盗んで行っても 知らずにいるほどゆっくり寝てみたい! どうだろう! その気持ちは? ああ、 想像するだけでも眠くなるようだ! 今着ている この着物を――重い、重いこの責任の着物を 脱ぎ捨ててしまったら。(ああ、うっとりする!) 私のこのからだが水素のように ふうわりと軽くなって、 高い、高い、大空へ飛んでゆくかもしれない!――「雲雀だ。」 下ではみんながそう言うかも知れない! ああ! ―――――――――― 死だ! 死だ! 私の願いはこれ たった一つだ! ああ! あっ、あっ、ほんとに殺すのか? 待ってくれ、 ありがたい神様、あ、ちょっと! ほんの少し、パンを買うだけだ、五-五-五銭でもいい! 殺すくらいのお慈悲があるなら! ―――――――――― 雨を含んだ生暖かい風邪の吹く晩だ。遠くに蛙の声がする。 光子から旭川に行ったというハガキが来た。名前は何でも、妹は外国人の居候だ! 兄は花盛りの都にいて、袖口の切れた綿入れを着ている! 妹は北海道の真ん中に六尺の雪に埋もれて讃美歌を歌っている! 午前三時、ハラハラと雨が落ちてきた。 十一日 日曜日 八時頃眼を覚ました。桜という桜が蕾一つ残さず咲きそろって、散るには早き日曜日。空はのどかに晴れ渡って、暖かな日だ。二百万の東京人がすべてを忘れて遊び暮らす花見は今日だ。 何となく気が 金田一君は花婿のようにソワソワしてセッセと洋服を着ていた。二人は連れだって九時頃外へ出た。 田原町で電車を捨てて浅草公園を歩いた。朝ながらに人出が多い。予はたわむれに一銭を投じて占いの紙を取った。吉と書いてある。予のたわむれはそれから始まった。吾妻橋から川蒸気に乗って千住大橋まで隅田川を遡った。初めて見た向島の長い土手は桜の花の雲にうずもれて見える。鐘ケ淵を過ぎると、眼界は多少田園の趣きを帯びてきた。筑波山も花曇りに見えない。見ゆる限りは桜の野! 千住の手前に赤く塗られた長い鉄橋があった。両岸は柳の緑。千住に上がって二人はしばし、そこらをぶらついた。予は、裾をはしょり、帽子をアミダにかぶって、しこたま友を笑わせた。 そこからまた船で鐘ケ淵まで帰り、花のトンネルになった土手の上を数知れぬ人を分けて、東京の方に向かって歩いた。予はその時も帽子をアミダにかぶり、裾をはしょって歩いた。何の意味もない、ただそんなことをしてみたかったのだ。金田一の外聞が悪がっているのが面白かったのだ。何万の晴れ着を着た人が、ゾロゾロと花のトンネルの下を歩く。中には、もう、酔っぱらっていろいろな道化た真似をしているのもあった。二人は一人の美人を見つけて、長いことそれと前後して歩いた。花はどこまでも続いている。人もどこまでも続いている。 無論面白いことのありようがない。昨夜の「パンの会」は盛んだったと平出君が話していた。あとで来た吉井は「昨晩、永代橋の上から酔っぱらって小便をして、巡査に咎められた、」と言っていた。なんでも、みんな酔っぱらって大騒ぎをやったらしい。 例のごとく題を出して歌をつくる。みんなで十三人だ。選の済んだのは九時頃だったろう。予はこのごろ真面目に歌などを作る気になれないから、相変わらずへなぶってやった。その二つ三つ。 わが いつも逢う赤き上着を着て歩く、男の ククと鳴る その前に 家を出て、野越え、山越え、海越えて、あわれ、どこにか行かんと思う。 ためらわずその手取りしに驚きて逃げたる女再び帰らず。 君が眼は万年筆の仕掛けにや、絶えず涙を流していたもう。 女見れば手をふるわせてタズタズとどもりし男、今はさにあらず。 ―――――――――――― 晶子さんは徹夜をして作ろうと言っていた。予はいいかげんな用をこしらえてそのまま帰ってきた。金田一君の部屋には碧海君が来ていた。予もそこへ行って一時間ばかり無駄話をした。そしてこの部屋に帰った。 ああ、惜しい一日をつまらなく過ごした! という悔恨の情がにわかに予の胸に湧いた。花を見るならなぜ一人行って、一人で思うさま見なかったか? 歌の会! 何というつまらぬ事だろう! 予は孤独を喜ぶ人間だ。生まれながらにして個人主義の人間だ。人と共に過ごした時間は、いやしくも、戦いでない限り、予には空虚な時間のような気がする。一つの時間を二人なり三人なり、あるいはそれ以上の人と共に費やす。その時間の空虚に、少なくとも半分空虚にみえるのは自然のことだ。 以前予は人の訪問を喜ぶ男だった。従って、一度来た人にはこの次にも来てくれるように、なるべく満足を与えて帰そうとしたものだ。何というつまらないことをしたものだろう! 今では人に来られても、さほど嬉しくもない。嬉しいと思うのは金の無い時にそれを貸してくれそうな奴の来た時ばかりだ。しかし、予はなるべく借りたくない。もし予が何ごとによらず、人から憐れまれ、助けらるることなしに生活することができたら、予はどんなに嬉しいだろう! これは敢えて金のことばかりではない。そうなったら予はあらゆる人間に口一つきかずに過ごすこともできる。 「つまらなく暮した!」そう思ったが、その後を考えるのが何となく恐ろしかった。机の上はゴチャゴチャしている。読むべき本もない。さしあたりせねばならぬ仕事は母やその他に手紙を書くことだが、予はそれも恐ろしいことのような気がする。何とでもいいからみんなの喜ぶようなことを言ってやって憐れな人たちを慰めたいとはいつも思う。予は母や妻を忘れてはいない、否、毎日考えている。そしていて予は今年になってから手紙一本とハガキ一枚やったきりだ。そのことはこないだの節子の手紙にもあった。節子は、三月でやめるはずだった学校にまだ出ている。今月はまだ月初めなのに、京子の小遣いが二十銭しかないと言ってきた。予はそのため社から少し余計に前借した。五円だけ送ってやるつもりだったのだ。それが、手紙を書くがいやさに一日二日と過ぎて、ああ……! すぐ寝た。 ―――――――――――― この日、朝に群馬県の新井という人が来た。「落栗」という雑誌を出すそうだ。 十二日 月曜日 今日も昨日に劣らぬうららかな一日であった。風なき空に花は三日の命を楽しんでまだ散らぬ。窓の下の桜は花の上に色浅き若芽をふいている。コブの木の葉は大分大きくなった。 坂を下りて田町に出ると、右側に一軒の下駄屋がある。その前を通ると、ふと、楽しい、賑やかな声が、なつかしい記憶の中からのように予の耳に入った。予の眼には広々とした青草の野原が浮かんだ。――下駄屋の軒の籠の中で雲雀が鳴いていたのだ。一分か二分の間、予はかの故郷の 思うに、予はすでに古き――然り! 古き仲間から離れて、自分一人の家を作るべき時機となった。友人というものに二つの種類がある。一つは互いの心に何か相求めるところがあっての交わり、そして一つは互いの趣味なり、意見なり、利益なりによって相近づいた交わりだ。第一の友人は、その互いの趣味なり、意見なり、利益なりあるいは地位なり、職業なりが違っていても、それが直接二人の間に、真面目に争わねばならぬような場合に立ち至らぬ限り、決して二人の友情の妨げとはならぬ。その間の交わりは比較的長く続く。 ところが第二の場合における友人にあっては、それとよほど趣きを異にしている。無論この場合において成り立ったものも、途中から第一の場合の関係に移って、長く続くこともある。が、大体この種の関係は、いわば、一種の取引関係である。商業的関係である。AとBとの間の直接関係でなくて、Aの所有する財産、もしくは、権利――即ち、趣味なり、意見なり、利益なり――と、Bの有するそれとの関係である。店なり、銀行なりの相互の関係は、相互の営業状態に何の変化も起こらぬ間だけ続く。いったんそのどちらかにある変化が起きると、取引はそこに断絶せざるを得ない。 まことに当たり前のことだ。 もしそれが第一の関係なら、友人を失うということは、不幸なことに違いない。が、もしもそれが第二の場合における関係であったなら、必ずしも幸福とは言えぬが、また敢えて不幸ではない。その破綻が受動的に起これば、その人が侮辱を受けたことになり、自動的に起したとすれば、勝ったことになる。 予がここに「古き仲間」と言ったのは、実は、予の過去においての最も新しい仲間である。否、あった。予は与謝野氏をば兄とも父とも、無論、思っていない。あの人はただ予を世話してくれた人だ。世話した人とされた人との関係は、した方の人がされた方の人より偉くている間、もしくは互いに別の道を歩いてる場合、もしくはした方の人がされた方の人より偉くなくなった時だけ続く。同じ道を歩いていて、そして互いの間に競争のある場合には絶えてしまう。予は今与謝野氏に対して別に敬意を持っていない。同じく文学をやりながらも、何となく別の道を歩いているように思っている。 予は与謝野氏とさらに近づく望みを持たぬと共に、敢えてこれと別れる必要を感じない。時あらば今までの恩を謝したいとも思っている。 晶子さんは別だ。予はあの人を姉のように思うことがある……この二人は別だ。 新詩社の関係から得た他の友人の多数は与謝野夫妻とはよほど趣きを異にしている。平野とはすでに喧嘩した。吉井は鬼面して人を嚇す放恣な空想化の亜流――最も憐れな亜流だ。もし彼らのいわゆる文学と、予の文学と同じものであるなら、予はいつでも予のペンを棄てるにためらわぬ。その他の人々は言うにも足らぬ―― 否。こんなことは何の要のないことだ。考えたって何にもならぬ。 予はただ予の欲することをなし、予の欲する所に行き……すべて予自身の要求に従えばそれでよい。 然り。予は予の欲するままに! That is all! All of all! そして、人に愛せらるな。人の恵みを受けるな。人と約束するな。 人の許しを乞わねばならぬ事をするな。決して人に自己を語るな。常に仮面をかぶっておれ。いつ何時でも戦のできるように―いつ何時でもその人の頭を叩き得るようにしておけ。一人の人と友人になる時は、その人といつか必ず絶交することあるを忘るるな。 十三日 火曜日 朝早くちょっと眼を覚ました時、女中が方々の雨戸をくっている音を聞いた。そのほかには何も聞かなかった。そしてそのまままた眠ってしまって、不覚の春の眠りを十一時近くまでも貪った。花曇りしたのどかな日。満都の花はそろそろ散り始めるであろう。おつねが来て、窓ガラスをきれいに拭いてくれた。 老いたる母から悲しき手紙がきた。―― 「このあいだみやざきさまにおくられしおてがみでは、なんともよろこびおり、こんにちかこんにちかとまちおり、はやしがつになりました。いままでおよばないもりやまかないいたしおり、ひにましきようこおがり、わたくしのちからでかでることおよびかねます。そちらへよぶことはできませんか? ぜひおんしらせくなされたくねがいます。このあいだむいかなのかのかぜあめつよく、うちにあめもり、おるところなく、かなしみに、きようこおぼいたちくらし、なんのあわれなこととおもいます。しがつふつかよりきようこかぜをひき、いまだなおらず、せつこは、あさはちじで、ごじかろくじかまでかえらず。おつかさんとなかれ、なんともこまります。それにいまはこづかいなし。いちえんでもよろしくそろ。なんとかはやくおくりくなされたくねがいます。おまえのつごうはなんにちごろよびくださるか? ぜひしらせてくれよ。へんじなきときはこちらしまい、みなまえりますからそのしたくなされませ。 はこだてにおられませんから、これだけもうしあげまいらせそろ。 かしこ。 しがつここのか。かつより。 いしかわさま。」 ヨボヨボした平仮名の、仮名違いだらけな母の手紙! 予でなければ ―――――――――――――― 今日は予にとって決して幸福な日ではなかった。起きた時は、何となく寝過ごしたけだるさはあるものの、どことなく気がのんびりして、身体中の血のめぐりのよどみなくすみやかなるを感じた。しかしそれもちょっとのことであった。予の心は母の手紙を読んだ時から、もう、さわやかではなかった。いろいろの考えが浮かんだ。 頭は何かこう、春の圧迫というようなものを感じて、自分の考えそのものまでが、ただもうまだるっこしい。「どうせ予にはこの重い責任を果たすアテがない。……むしろ早く絶望してしまいたい。」こんな事が考えられた。 そうだ! 三十回位の新聞小説を書こう。それなら或いは案外早く金になるかもしれない! 頭がまとまらない。電車の切符が一枚しかない。とうとう今日は社を休むことにした。 貸本屋が来たけれど、六銭の金がなかった。そして、「空中戦争」という本を借りて読んだ。 新しき都の基礎 やがて世界の戦は来らん! フェニックスのごとき空中軍艦が空に群れて、 その下にあらゆる都府が毀たれん! 戦は長く続かん! 人々の半ばは骨となるならん! しかる後、哀れ、しかる後、我らの 「新しき都」はいずこに建つべきか! 滅びたる歴史の上にか! 思考と愛の上にか? 否、否。 土の上に。然り、土のうえに。何の――夫婦という 定まりも区別もなき空気の中に。 果てしれぬ蒼き、蒼き空のもとに! 十四日 水曜日 晴。佐藤さんに病気届をやって、今日と明日休むことにした。昨夜金田一君から、こないだの二円返してくれたので、今日は煙草に困らなかった。そして書き始めた。代は、「ホウ、」あとで「木馬」と改めた。 創作の興と性欲とはよほど近いように思われる。貸本屋が来て妙な本を見せられると、なんだか読んでみたくなった。そして借りてしまった。一つは「花の 夜は金田一君の部屋に中島君と、噂に聞いていた小詩人君――内山舜君が来たので、予も行った。 内山君の鼻の恰好たらない! 不恰好な里芋を顔の真ん中にくっつけて、その先を削って平たくしたような鼻だ。よくしゃべる、たてつづけにしゃべる。まるで髭をはやした 雨が降ってきた。もう十時近かった。中島君は社会主義者だが、彼の社会主義は貴族的な社会主義だ――彼は俥で帰って行った。そして内山君――詩人は本当の社会主義者だ……番傘を借りて帰っていくその姿はまことに詩人らしい恰好を備えていた…… 何か物足らぬ感じが予の胸に――そして金田一君の胸にもあった。二人はその床の間の花瓶の桜の花を、部屋いっぱいに――敷いた布団の上に散らした。そして子供のようにキャッキャ騒いだ。 金田一君に布団をかぶせてバタバタ叩いた。そして予はこの部屋に逃げてきた。そしてすぐ感じた。「今のはやはり現在に対する一種の破壊だ!」 「木馬」を三枚書いて寝た。節子が恋しかった――しかしそれは侘しい雨の音のためではない。「花の朧夜」を読んだためだ! 中島孤島君は予の原稿を売ってくれると言った。 十五日 木曜日 否! 予における節子の必要は単に性欲のためばかりか? 否! 否! 恋は醒めた。それは事実だ。当然なる事実だ――悲しむべき、しかしやむを得ぬ事実だ! しかし恋は人生のすべてではない。その一部分だ。恋は遊戯だ。歌のようなものだ。人は誰でも歌いたくなる時がある。そして歌ってる時はたのしい。が、人は決して一生歌ってばかりはおられぬものである。同じ歌ばかり歌ってると、いくら楽しい歌でも飽きる。またいくら歌いたくっても歌えぬ時がある。 恋は醒めた。予は楽しかった歌を歌わなくなった。しかしその歌そのものは楽しい。いつまでたっても楽しいに違いない。 予はその歌ばかりを歌ってることに飽きたことはある。しかし、その歌を、いやになったのではない。節子は誠に善良な女だ。世界のどこにあんな善良な、やさしい、そしてしっかりした女があるか? 予は妻として節子よりよき女を持ち得るとはどうしても考えることができぬ。予は節子以外の女を恋しいと思ったことはある。他の女と寝てみたいと思ったこともある。現に節子と寝ていながらそう思ったこともある。そして予は寝た――他の女と寝た。しかしそれは節子と何の関係がある? 予は節子に不満足だったのではない。人の欲望が単一でないだけだ。 予の節子を愛してることは昔も今も何の変わりがない。節子だけを愛したのではないが、最も愛したのはやはり節子だ。今も――ことにこのごろ予はしきりに節子を思うことが多い。 人の妻として、世に節子ほど可哀想な境遇にいるものがあろうか?! 現在の夫婦制度――すべての社会制度は間違いだらけだ。予はなぜ親や妻や子のために束縛されねばならぬか? 親や妻や子はなぜ予の犠牲とならねばならぬか? しかしそれは予が親や節子や京子を愛してる事実とはおのずから別問題だ。 ―――――――――――――― まことに厭な朝であった。恋のごとくなつかしい春の眠りを捨てて起き出でたのは、もう十時過ぎであった。雨――強い雨が窓にしぶいていた。空気はジメジメしている。便所に行って驚いて帰って来た。昨日まで冬木のままであった木がみな浅緑の芽をふいている。西片町の木立は昨日までの花衣を脱ぎ捨てて、雨の中に煙るような若葉の薄物をつけている。 一晩の春の雨に世界は緑色に変わった! 今朝また下宿屋の催促! こういう生活をいつまで続けねばならぬか? この考えはすぐに予の心を弱くした。何をする気もない。そのうちに雨は晴れた。どこかへ行きたい。そう思って予は外に出た。金田一君からまさかの時に質に入れて使えと言われていたインバネスを松坂屋へ持って行って、二円五十銭借り、五十銭は先に入れているのの利子に入れた。そうして予はどこに行くべきかを考えた。郊外へ出たい――が、どこにしよう? いつか金田一君と花見に行ったように、吾妻橋から川蒸気に乗って千住大橋へ行き、田舎めいた景色の中をただ一人歩いてみようか? 或いはまた、もしどこかに空き家でもあったら、こっそりその中へ入って夕方まで寝てみたい! とにかく予のその時の気持ちでは人の沢山いるところは厭であった。予はその考えを決めるために本郷館―― 雨の後の人少なき上野! 予はただそう思って行った。桜という桜の木は、花が散りつくしてガクだけ残っている――汚い色だ。楓の緑! 泣いたあとの顔のような醜さの底から、どことなくもう 汽車に乗りたい! そう予は思った。どこまでというアテもないが、乗って、そしてまだ行ったことのない所へ行きたい! 幸い、ふところには三円ばかりある。 ああ! 汽車に乗りたい! そう思って歩いていると、ポツリポツリ雨が落ちてきた。 雨は別に本降りにもならずに晴れたが、その時はもう予は広小路の商品館の中を歩いていた。そして、馬鹿な! と思いながら、その中の洋食店へ入って西洋料理を食った。 原稿紙、帳面、インクなどを買って帰った時、金田一君も帰って来た。そして一緒に湯に入った。 「木馬」! 十六日 金曜日 何という馬鹿なことだろう! 予は昨夜、貸本屋から借りた徳川時代の好色本「花の朧夜」を三時頃まで帳面に写した――ああ、予は! 予はその激しき楽しみを求むる心を制しかねた! 今朝は異様なる心の疲れを抱いて十時半頃に眼をさました。そして宮崎君の手紙を読んだ。ああ! みんなが死んでくれるか、予が死ぬか。二つに一つだ! 実際予はそう思った。そして返事を書いた。予の生活の基礎は出来た、ただ下宿をひき払う金と、家を持つ金と、それから家族を呼び寄せる旅費! それだけあればよい! こう書いた。そして死にたくなった。 やろうやろうと思いながら、手紙を書くのが厭さに――恐ろしさに、今日までやらずにおいた一円を母に送った――宮崎君の手紙に同封して。 予は昨夜の続き――「花の朧夜」を写して、社を休んだ。 夜になった。金田一君が来て、予に創作の興を起させようといろいろな事を言ってくれた。予は何ということなく、ただもうむやみに滑稽なことをした。 「自分の将来が不確かだと思うくらい、人間にとって安心なことはありませんね! ハ、ハ、ハ、ハ!」 金田一君は横に倒れた。 予は胸の肋骨をトントン指で叩いて、「僕が今何を――何の曲を弾いてるか、わかりますか?」 あらん限りの馬鹿真似をして、金田一君を帰した。そしてすぐペンをとった。三十分過ぎた。予は予がとうてい小説を書けぬことをまた真面目に考えねばならなかった。予の未来に何の希望のないことを考えねばならなかった。そして予はまた金田一君の部屋に行って、数限りの馬鹿真似をした。胸に大きな人の顔を書いたり、いろいろな顔をしたり、口笛でうぐいすやホトトギスの真似をしたり――そして最後に予はナイフを取り上げて芝居の人殺しの真似をした。金田一君は部屋の外に逃げ出した! ああ! 予はきっとその時あの恐ろしいことを考えていたったに相違ない! 予はその部屋の電灯を消した、そして戸袋の中にナイフを振り上げて立っていた!―― 二人がさらに予の部屋で顔を合わした時は、どっちも今のことをあきれていた。予は、自殺ということは決してこわいことでないと思った。 かくて、夜、予は何をしたか? 「花の朧夜」! 二時頃だった。小石川の奥のほうに火事があって、真っ暗な空にただ一筋の薄赤い煙がまっすぐに立ち昇った。 火! ああ! 十七日 土曜日 十時頃に並木君に起された。予は並木君から時計を質に入れてまだ返せずにいる。その並木君の声で、深い、深い、眠りの底から呼び覚まされた時、予は何ともいえぬ不愉快を感じた。罪を犯した者が、ここなら安心とどこかへ隠れていたところへ、巡査に踏み込まれたならこんな気持ちがするかもしれぬ。 どうせ面白い話のありようはない。無論時計の催促を受けたんでも何でもないが、二人の間には深い性格のへだたりがある……ゴリキーのことなどを語り合って、十二時頃別れた。 今日こそ必ず書こうと思って社を休んだ――否、休みたかったから書くことにしたのだ。それはともかくも予は昨夜考えておいた「赤インク」というのを書こうとした。予が自殺することを書くのだ。ノート三枚ばかりは書いた。……そして書けなくなった! なぜ書けぬか? 予はとうてい予自身を客観することができないのだ、否。とにかく予は書けない――頭がまとまらぬ。 それから、「茂吉イズム」という題でかつて「入京記」に書こうと思っていたことを書こうとしたが…… 風呂で金田一君に会った。今神保博士から電話がかかってきたが、樺太行きが決まりそうだという。金田一君も驚いているし、予も驚かざるを得なかった。行くとすればこの春中だろうということだ。樺太庁の嘱託として「ギリヤーク」「オロツコ」などいう土人の言葉を調べるに行くのだそうだ。 風呂から上ってきて机に向かうと悲しくなった。金田一君が樺太へ行きたくないのは、東京で生活することのできるためだ。まだ独身でいろいろな望みがあるためだ。もし予が金田一君だったらと考えた。ああ、ああ! 間もなく金田一君が、「独歩集 第二」を持って入って来た。そして泣きたくなったと言った。そしてまた今日一日予のことばかり考えていたと言って、痛ましい眼つきをした。 金田一君に独歩の「疲労」その他二三篇を読んでもらって聞いた。それから樺太のいろいろの話を聞いた。アイヌのこと、朝空に羽ばたきする鷲のこと、船のこと、人の入れぬ大森林のこと…… 「樺太まで旅費がいくらかかります?」と予は問うた。 「二十円ばかりでしょう。」 「フーン。」と予は考えた。そして言った。 「あっちへ行ったら何か僕にできるような口を見つけてくれませんか? 巡査でもいい!」 友は痛ましい眼をして予を見た。 一人になると、予はまた厭な考えごとを続けなければならなかった。今月ももう半ば過ぎた。社には前借があるし……そして、書けぬ! 「スバル」の歌を直そうかとも思ったが、紙をのべたたけで厭になった。 空き家へ入って寝ていて、巡査に連れられていく男のことを書きたいと思ったが、しかし筆をとる気にはなれぬ。 泣きたい! 真に泣きたい! 「断然文学を止めよう。」と一人で言ってみた。 「止めて、どうする? 何をする?」 「Death」と考えるほかはないのだ。 実際予は何をすればよいのだ? 予のすることは何かあるだろうか? いっそ田舎の新聞へでも行こうか! しかし行ったとてやはり家族を呼ぶ金は容易に出来そうもない。そんなら、予の第一の問題は家族のことか? とにかく問題は一つだ。いかにして生活の責任の重さを感じないようになろうか? ――これだ。 金を自分が持つか、然らずんば、責任を解除してもらうか、二つに一つ。 おそらく、予は死ぬまでこの問題を背負って行かねばならぬだろう! とにかく寝てから考えよう。(夜一時。) 十八日 日曜日 早く眼は覚ましたが、起きたくない。戸が閉まっているので部屋の中は薄暗い。十一時までも床の中にモゾクサしていたが、社に行こうか、行くまいかという、たった一つの問題をもてあました。行こうか? 行きたくない。行くまいか? いや、いや、それでは悪い。何とも結末のつかぬうちに女中がもう隣の部屋まで掃除してきたので起きた。顔を洗ってくると、床を上げて出て行くおつねの奴。 「掃除はお昼過ぎにしてやるから、ね、いいでしょう?」 「ああ。」と予は気抜けしたような声で答えた。 「――してやる? フン。」と、これは心のうち。 節子からハガキが来た。京子が近頃また身体の具合がよくないので医者にみせると、また胃腸が悪い――しかも慢性だと言ったとのこと。予がいないので心細い。手紙がほしいと書いてある。 とにかく社に行くことにした、一つは節子の手紙を見て気を変えたためでもあるが、また、「今日も休んでる!」と女中どもに思われたくなかったからだ。 「なーに、厭になったら途中からどっかへ遊びに行こう!」そう思って出たが、やっぱり電車に乗ると、切符を数寄屋橋に切らせて、社に行ってしまった。 三つぐらいの可愛い女の子が乗っていた。京子のことがすぐ予の心に浮かんだ。節子は朝に出て夕方に帰る。その一日、狭苦しい家の中はおっかさんと京子だけ! ああ、おばあさんと孫! 予はその一日を思うと、眼がおのずからかすむを覚えた。子供のたのしみは食い物のほかにない。その単調な、薄暗い生活に 不消化物がいたいけな京子の口から腹に入って、そして弱い胃や腸を痛めている様が心に浮かんだ! にせ病気をつかって五日も休んだのだから、予は多少敷居の高いような気持ちで社に入った。無論何の事もなかった。そして、ここに来ていさえすれば、つまらぬ考えごとをしなくてもいいようで、何だか安心だ。同時に、何の係累のない――自分の取る金で自分一人を処置すればよい人たちがうらやましかった。 新聞事業の興味が、校正の合間合間に予を刺激した。予は小樽が将来最も有望な都会なことを考えた。そして、小樽に新聞を起して、あらん限りの活動をしたら、どんなに愉快だろうと思った。 帰りに唖の女を電車の中で見た。「小石川」と手帳へ書いて、それを車掌に示して、乗換切符をもらっていた。 妹――親兄弟に別れ、 兄様に言いつけられて、あの山道の方など、菫を探しに歩きました当時のことを追懐いたします。兄様もあるいはその当時の有様を心にお辿りになることがおありかもしれません! ……私の机の上に可愛らしい福寿草があります。それを見ていますと、今日、ふと故郷が思い出されてなりませんの。よく菫や福寿草を探しに、あの墓場のほとりを歩きましたっけ! ……そして、いろいろなことを思い出しましたの。兄様に叱られた昔のことを思っては、新しく恨んでもみました――許して下さいませ! 今は叱られたくても及びません! 「なぜあの時、甘んじて兄様に叱られなかったでしょう? 今になってはそれがこの上もなく、 悔しゅうございます。もう一度、兄様に叱られてみたくって! しかしもう及びません! ……実際私の心がけは間違ってましたねえ! ……兄様は今渋民の誰かとお便りなすっていらっしゃるの? 私、秋浜のきよ子さんにお便り出したいと存じておりますが、北海道へ参ってからまだ一度も出しませんの。…… 「それから私どもねえ、五月中頃は婦人会や修養会がございまして、また小樽や余市方面へ参ります……」 ……予の眼はかすんだ。この心持ちをそのまま妹に告げたなら、妹はどんなに喜ぶであろう! 現在の予に、心ゆくばかり味わって読む手紙は妹のそればかりだ。母の手紙、節子の手紙、それらは予にはあまり悲しい、あまり辛い。なるべくなら読みたくないとすら思う。そしてまた、予には以前のように心と心の響き合うような手紙を書く友人がなくなった。時々消息する女――二三人の若い女の手紙――それも懐かしくないわけではないが、しかしそれは偽りだ。……妹! 予のただ一人の妹! 妹の身についての責任はすべて予にある。しかも予はそれを少しも果たしていない。――おととしの五月の初め、予は渋民の学校でストライキをやって免職になり、妹は小樽にいた姉のもとに厄介になることになり、予もまた北海道へ行って、何かやるつもりで、一緒に函館まで連れてってやった。津軽の海は荒れた。その時予は船に酔って蒼くなってる妹に清心丹などを飲まして、介抱してやった。――ああ! 予がたった一人の妹に対して、兄らしいことをしたのは、おそらく、その時だけなのだ! 妹はもう二十二だ。当たり前ならば無論もう結婚して、可愛い子供でも抱いてるべき年だ。それを、妹は今までもいくたびか自活の方針をたてた。不幸にしてそれは失敗に終った。あまりに兄に似ている不幸な妹は、やはり現実の世界に当てはまるように出来ていなかった! 最後に妹は神を求めた。否、おそらくは、神によって職業を求めた。光子は、今、冷やかな外国婦人のもとに養われて、「神のため」に働いている。来年は試験を受けて名古屋のミッション・スクールへ入り、「一生を神に捧げて」伝道婦になるという! 兄に似た妹は果たして宗教家に適しているだろうか! 性格のあまりに近いためでがなあろう。予と妹は小さい時から仲が悪かった。おそらくこの二人のくらい仲の悪い兄妹はどこにもあるまい。妹が予に対して妹らしい口を利いたことはあったが、予はまだ妹がイジコの中にいた時から、ついぞ兄らしい口を利いたことはない! ああ! それにもかかわらず。妹は予を恨んでいない。また昔のように叱られてみたいと言ってる――それがもうできないと悲しんでる! 予は泣きたい! 渋民! 忘れんとして忘れ得ぬのは渋民だ! 渋民! 渋民! 我を育て、そして迫害した渋民! ……予は泣きたい、泣こうとした。 しかし涙が出ぬ! ……その生涯の最も大切な十八年の間を渋民に送った父と母――悲しい年寄りだちには、その渋民は余りに辛く痛ましい記憶を残した。死んだ姉は渋民に三年か五年しかいなかった。二番目の岩見沢の姉は、やさしい心と共に渋民を忘れている。思い出すことを恥辱のように感じている。そして節子は、盛岡に生まれた女だ。予と共に渋民を忘れ得ぬものはどこにあるか? 広い世界に光子一人だ! ―――――――――――――― 今夜、予は妹――哀れなる妹を思うの情に堪えぬ。会いたい! 会って兄らしい口を利いてやりたい! 心ゆくばかり渋民のことを語りたい。二人とも世の中の辛さ、悲しさ、苦しさを知らなかった何年の昔に帰りたい! 何もいらぬ! 妹よ! 妹よ! 我らの一家がうち揃って、楽しく渋民の昔話をする日は果たしてあるだろうか? いつしか雨が降りだして、雨だれの音が侘びしい。予にしてもし父――すでに一年便りもせずにいる父と、母と、光子と、それから妻子とを集めて、たとい何のうまいものはなくとも、一緒に晩餐をとることができるなら…… 金田一君の樺太行きは、夏休みだけ行くのだそうだ。今日は言語学会の遠足で大宮まで行って来たとのこと。 十九日 月曜日 下宿の虐待は至れり尽せりである。今朝は九時頃起きた。顔を洗ってきても火鉢に火もない。一人で床を上げた。マッチで煙草をのんでいると、子供が廊下を行く。言いつけて、火と湯をもらう。二十分も経ってから飯を持ってきた。シャモジがない。ベルを押した。来ない。また押した。来ない。よほど経ってからおつねがそれを持ってきて、もの言わずに投げるように置いて行った。味噌汁は冷たくなっている。 窓の下にコブの木の花が咲いている。昔々、まだ渋民の寺にいたころ、よくあの木の枝を切ってはパイプをこしらえたものだっけ! 女中などが失敬な素振りをすると、予はいつでも、「フン、あの畜生! 俺が金をみんな払って、そして、奴等にも金をくれてやったら、どんな顔をしておべっかを使いやがるだろう!」と思う。しかし、考えてみると、いつその時代が俺に来るのだ? 「小使豊吉」後に「坂牛君の手紙」と題を改めて書き出したが、五行も書かぬうちに十二時になって社に出かけた。 変ったことなし、老小説家三島老人が何かと予に親しみたがってる様子が面白い。給仕の小林は、「あなたがスバルという雑誌に小説をお書きになったのは何月ですか?」と聞いていたっけ。 帰ってきて、「坂牛君の手紙」をローマ字で書き出したが、十時頃には頭が疲れてしまった。 二十日 火曜日 廊下でおつねが何か話している。その相手の声は予の未だ聞いたことのない声だ。細い初々しい声だ。また新しい女中が来たなと思った――それは七時頃のこと――この日第一に予の意識にのぼった出来事はこれだ。 うつらうつらとしていると、誰かしら入って来た。「きっと新しい女中だ。」――そう夢のように思って、二三度ゆるやかな呼吸をしてから眼を少しばかり開いてみた。 思ったとおり、十七ぐらいの丸顔の女が、火鉢に火を移している。「おさださんに似た、」とすぐ眼をつぶりながら、思った。おさださんというのは、渋民の郵便局の娘であった。あのころ――三十六年――たしか十四だったから、今は十――十――そうだ、もう二十歳になったのだ……どこへお嫁に行ったろう? そんなことを考えながら金矢七郎君を思い出した。そしてウトウトした。 すぐまた眼がさめた――と言っても眼をあく程すっかりではない。手荒く障子をあけておつねが入って来た。そして火鉢の火を持って行く、予が眼をあくと、 「貴方の所へはあとで持って来ます。」 「虐待しやがるじゃないか?」 と、予は、胸の中でだけ言ったつもりだったが、つい口に出てしまった。おつねは顔色を変えた。そして何とか言った。予は「ムヤ、ムヤ」言って寝返りをした! 午前中、頭がハッキリしていて、「坂牛君の手紙」を二枚だけ書いた。そして社に行った。 昨夜川崎の手前に汽車の転覆があったので、社会部の人たちはテンテコ舞いをしている。 例刻に帰った。間もなく平出君から電話。短歌号の原稿の催促だ。いい加減な返事をしたが、フン! ツマラナイ、歌など! そう思うと、家にくすぶってるもつまらいという気になって、ひとり出かけた、五丁目の活動写真で九時までいた。それから一時間はアテもなく電車の中。 ―――――――――――――― 今朝、肩掛を質屋に持って行って六十銭借りた。そして床屋に入って頭を五分刈りにし、手拭とシャボンを買って、すぐその店の前の湯屋に入ろうとすると、「今日は検査の日だから、十一時ごろからでなくては湯がたたぬ、」とその店の愛嬌のあるカミさんが教えてくれた。 二十一日 水曜日 昨夜枕の上で天外の「長者星」を少し読んだ。実業界のことを書こうと思って一ヵ年間研究したという態度が既に間違っている。第二義の小説……が、この作家は建築家のような、事件を組み立てる上の恐るべき技量を持っている。空想の貧弱な作家の及ぶところでない。 そうしてる所へ金田一君が、「お湯があるか、」と言って入って来て、上田敏さんが何かの雑誌へ「小説は文学に非ず、」という論文を出すそうだという話をした。「それ、ごらんなさい!」と予は言った。「あの人もとうとうその区別をしなければならなくなってきた。時は文学の最も純粋なものだというあの人のクラシカルな意見なり趣味なりを捨てることも出来ず、さりとて、新文学の権威を認めぬわけにいかなくなってきた。そこでそんな二元的な区別を立てなくちゃならなくなったんでしょう。――」 ―――――――――――――― 今日から三階はまたおきよさんの番だ。早く起きた。 遂に葉桜の頃とはなった。窓をあけると、煙るような若葉の色が眼を刺激する。 昨日は電車の中で二人まで夏帽を被った人を見た。夏だ! 九時に台町の湯屋へ行った。ここは去年東京に来て赤心館にいた頃、よく行きつけた湯屋だ。大きい姿見、気持ちよき噴霧器、何の変りはない。ただあの頃いた十七ばかりの男好きらしい女が、今日は番台の上にいなかった。一枚ガラスの窓には朝のスガスガしい日光に青葉の影がゆらめいていた。予は一年前の心持になった。三助も去年の奴だ。……そして予は激しい東京の夏がすぐ眼の前に来てることを感じた。赤心館の一ト夏! それは予が非常な窮迫の地位に居ながらも、そうして、たとい半年の間でも家族を養わねばならぬ責任から逃れているのが嬉しくて。そうだ! なるべくそれを考えぬようにして「半独身者」の気持ちを楽しんでいた時代であった。そのころ関係していた女をば、予は間もなく捨ててしまった。――今は浅草で芸者をしている。いろいろのことは変った。予はこの一年間に幾人かの新しい友を得、そうして捨てた。……予は、その頃より健康になった身体をセッセと洗いながら、いろいろの追懐に耽った。――一年間の激しい戦い! ……(※以下、縦区切り線まで英文)そして、恐ろしい夏がまた予に! 一文無しの小説家にやってくる! 恐ろしい夏が! ああ! 肉体的なたたかいの大きな苦痛と深い悲しみと一緒に、他方また若いニヒリストの底なしの歓喜といっしょに! 湯屋の門を出ると昨日予に石鹸を売った表情たっぷりの女がどこかおだやかな好意のこもった素振りで予に「おはようございます」と言った。 入浴と追憶とは予にいくらか熱した若い快活さを与えた。予は若い。そして、ついに、生活はそれほど暗くも苦しくもない。日は照っている。月は静かだ。予が金を送るか、彼らを東京に呼ぶかしなければ、彼ら――予の母と妻とは別の方法で食ってくだろう。予は若い、若い、若い。予にはペンと頭脳と眼と情と知とがある。ただそれだけ。それが全部だ。下宿の主人が予をこの部屋から追い出すなら、予はどこへでも行く。この首府には下宿やホテルはたくさんある。今日、予には五厘銅貨一枚しかない。だがそれがなんだ。ナンセンスだ! 東京にはずいぶんたくさん作家がいる。それが予にどうだというのだ。なんでもない。彼らは指の骨と筆で書いている。だが予はインキとGペンで書かねばならぬ! ただそれだけだ。ああ、焼けるような夏と緑色のたたかい! ―――――――――――――― 今日から汽車の時間改正のため第一版の締切が早くなり、ために第二版の出来る迄居ることになった。出勤は十二時、退けは六時。 夜、金田一君の部屋に中村君が来た。行って話す。この人も学校を出ると多分朝日へ入るようになるだろうとのこと。 平出から原稿催促の電話。 二十二日 木曜日 昨夜早く寝たので、今日は六時頃に起きた。そして歌を作った。晴れた日が午後になって曇った。 夜、金田一君と語り、歌を作り、十時頃また金田一君の部屋へ行って、作った歌を読んで大笑い、さんざんふざけ散らして、大騒ぎをし、帰って来て寝た。 二十三日 金曜日 六時半頃に起きて洗面所に行くと、金田一君が便所で挨拶されたという十九番の部屋の美人が今しも顔を洗って出てゆくところ。遅かった由良之助! その女の使った金盥で顔を洗って、「何だ、バカなことをしやがるな!」と心の中。 歌を作る。予が自由自在に駆使することの出来るのは歌ばかりかと思うと、いい心持ではない。 十一時ごろから雨が降り出した。社では木村、前川の両老人が休んだので第一版の校了まで煙草ものめぬ忙しさ。 帰る頃からバカに寒くなってきた。それに腹がへっているので電車の中で膝小僧が震えた。中学時代の知人長沼君に会った。生白い大きな顔に、高帽をかぶって、今風の会社員か役人風のスタイルをして、どうやら子供のありそうな横柄な様子だ。こいつどうせ来る奴でないからと番地を書いて名刺をくれてやった。 近頃電車の中でよく昔の知人に会う。昨日も数寄屋橋で降りる時、出口に近く腰かけていた角帯の青年、 「失礼ですが貴方は盛岡にいらしった石――」 「そうです、石川です。」 「私は 柴内薫、あの可愛かった子供! どこにいると聞いたら、赤坂の多田――もとの盛岡中学の校長――の家にいると言った。こっちの住所は教える暇もなく予は降りてしまった。 金田一君はしきりに明日のレクチュアの草稿をつくっているらしい。予は帰って来て飯が済むとすぐとりかかった歌を作り始めた。この間からの分を合わせて、十二時頃までかかって七十首にして、「莫復問七十首」と題して快く寝た。 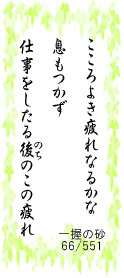 何に限らず一日暇なく仕事をしたあとの心持は例うるものもなく楽しい。人生の真の深い意味は蓋しここにあるのだろう! 二十四日 土曜日 晴れた日ではあったが、北風は吹いて寒暖計は六十二度八分しか昇らなかった。 「スバル」の募集の歌「秋」六百九十八首中から、午前のうちに四十首だけ選んだ。社に行く時それと昨夜の「莫復問七十首」とを平出君のところに置いて行った。 今日の記事の中に練習艦隊太平洋横断の通信があった。その中に春季皇霊祭の朝、艦員皆甲板に出て西の空を望んで皇霊を拝したということがあった。耳の聞えない老小説家の三島じいさん、「西の空では日本の方角ではない」と言って頑としてきかなかった。それから前川じいさんは昨日無断欠勤したというので、加藤「ラウンド・アイズ」と喧嘩していたっけ。この人は予の父に似た人なのだ。 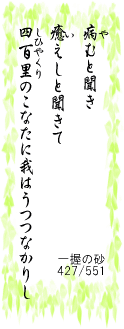 少し遅くなって帰った。机の上には原稿紙の上に手紙らしいもの――胸を躍らして電灯のネジをひねると、それは札幌の橘智恵子さんから――! 退院の知らせのハガキをもらってから予はまだ返事を出さずにいたったのだ。 「函館にてお目にかかりしは僅かの間に候いしがお忘れもなくお手紙……お嬉しく」――と書いてある。「この頃は外を散歩するくらいに相成候」と書いてある。「昔偲ばれ候」と書いてある。そして「お暇あらばハガキなりとも――」と書いてある。 金田一君が入ってきた。今日のレクチュアの成績がよかったとみえてニコニコしている。話はいろいろであったが、友の眼の予に語るところは、「創作をやれ」ということであった。「足跡の後を書け、」と言った。そして一ヶ月前の予の興奮時代を駆っ立てその眼は予の現在の深き興味を失った気持ちを責むるごとくであった。予は言った。 「だが、金田一さん、俺だってすぐ貴方の希望に沿い度い……が、俺には今敵がなくなった! どうも張り合いがない。」 「敵! そうですねえ!」 「あの頃の敵は太田君だった。実際です。」 「そうでしたねえ!」 「大田と俺の取引きは案外早く終ってしまった。 『二元、二元、猶説き得ずば三元を樹つる意気込み、賢き友かな』 私はこの歌を作るとき誰を思い浮かべたと思います? 上田さんと、それから太田君です。まだこの外にも太田に対する思想上の絶交状を意味する歌を三つ四つ作りましたよ。」 「つまり、もう太田君を棄てたんですか?」 「敵ではなくなったんです。だから俺はこうガッカリしてしまったんです。敵! 敵! オーソリティのない時代には強い敵がなくちゃダメですよ。そこへ行くと独歩なんかはえらい、実にえらい。」 こんな話も、しかし、予の心臓に少しの鼓動をも起さなかった。 二十五日 日曜日 予の現在の興味は唯一つある。それは社に行って二時間も三時間も息もつかずに校正することだ。手が空くと頭が何となく空虚を感ずる。時間が長くのみ思える。はじめ予の心を踊り立たした輪転機の響きも、今では馴れてしまって強くは耳に響かない。今朝これを考えて悲しくなった。 予はすべてのものに興味を失っていきつつあるのではあるまいか? すべてに興味を失うということは、即ちすべてから失われるということだ。"I have had lost from everything!" こういう時期がもし予に来たら! 「駆け足をして息が切れたのだ。俺は今並み足で歩いている、」と予は昨晩友に語った。 今日は砲兵工廠の大煙突が煙を吐いていない。 ―――――――――――――― 社に行って月給を受け取った。現金七円と十八円の前借証。 先月は二十五円の顔を見ただけで佐藤さんに返してしまい、結局一文も持って帰ることが出来なかったが…… 日曜だから第一版だけで予は帰った。そして四時頃駿河台の与謝野氏を訪ねた。主人は俳優養成所の芝居を見に行って留守だったが、二階で晶子さんと話していると吉井君が来た。平山良子の話が出た。 晶子さんは、今度の短歌号に出る与謝野氏の歌は物議を醸しそうだと言う。どうしてですと言うと、 「こないだ二人で喧嘩したんですよ。ウチが、あなた、 「ハ、ハ、ハ! そうですか。」 「それから、あの、山川さんがおなくなりになりましたよ。」 「山川さんが……!」 「ええ、……今月の十五日に……」 薄幸なる女詩人山川登美子女史は遂に死んだのか?! ………! 与謝野氏が帰って来て間もなく予は辞した。何やらの話の続きで「ハ、ハ、ハ」と笑いながら外に出て予は、二三歩歩いて「チェ、」と舌打ちした。「よし! 彼らと僕とは違ってるのだ。フン! 見ていやがれ、バカヤロ奴!」 電車の二十回券を買った。 頭が少し痛い。金田一君を誘って散歩に出かけた。本郷三丁目で、 「どこへ行きます?」 「そう!」 坂本行きの乗換切符を切らせて吉原へ行った。金田一君には二度目か三度目だが、予は生まれて初めてこの不夜城に足を入れた。しかし思ったより広くもなく、たまげる程のこともなかった。廓の中をひと巡り廻った。さすがに美しいには美しい。 「夜眼を覚ますと雨だれの音が何だか隣室のさざめごとのようで、美しい人が枕元にいるような……縹渺たる心地になることがある、」というようなことを金田一君が言い出した。 「縹渺たる心地!」と予は言った。「私はそんな心地を忘れてから何年になるかわからない!」 友はまた、「私もいつか是非あそこへ行ってみたい」というようなことを言った。 「大にいい!」と予は言った。「行った方がいいですよ。そして結婚したらどうです?」 「相手さえあればいつでも。だが結婚したらあんな所へ行かなくてもいいかも知れませんね!」 「そうじゃない。僕はやっぱり行った方がいいと思う。」 「そうですねえ!」 「なんですねえ、浅草は、いわば、単に肉欲の満足を得るところだから、相手がつまりはどんな奴でも構わないが、吉原なら僕はやはり美しい女と寝たい。あそこには歴史的連想がある。一帯が美術的だ。……華美を尽した部屋の中で、燃え立つような 「ああ、堪らなくなる!」 「吉原へ行ったら美人でなきゃいけませんよ。浅草ならまた何でもかんでも肉体の発育のいい、オーガンの完全な奴でなければいけない……」 二人は一時間近くもその「縹渺たる気持ち」や、盛岡のある女学生で吉原にいるという久慈某のことを語って寝た。 二十六日 月曜日 眼を覚ますと火鉢の火が消えていた。頭の中がジメジメ湿っているような心持ちだった。 何とかして明るい気分になりたいというようなことを考えているところへ並木君のハガキが着いた。 それを見ると予の頭はすっかり暗く、冷たく、湿り返ってしまった。借りて質に入れてある時計を今月中に返してくれまいかというハガキだ。 ああ! 今朝ほど予の心に死という問題が直接に迫ったことがなかった。今日社に行こうか行くまいか……いや、いや、それよりも先ず死のうか死ぬまいか? ……そうだ、この部屋ではいけない。行こう、どこかへ行こう…… 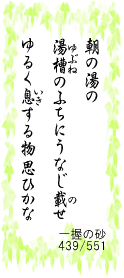 湯に行こうという考えが起こった。それは自分ながらこの不愉快な気分に堪えられなかったのだ。先日行った時のいい気持ちが思い出されたのだ。とにかく湯に行こう。そしてから考えることにしよう。そして予は台町の湯屋に行った。その時までは全く死ぬつもりでいたのだ。 湯の中は気持ちがいい。予は、出来るだけ長くそこにいようと思った。ここさえ出れば恐ろしい問題が待ち構えていて、すぐにも死ぬか何かせねばならぬようで、温かい湯に浸かっている間だけが自分の身体のような気がした。予は長くいようとした。しかし案外に早く身体も洗わさってしまう。 どうしよう! あがろうか? それとももう少し入っていようか? 上ったら一体どこに行こう? ガラス戸越しに番台の女が見える。それは去年この湯によく行った頃いた娘、この間行った時はどうしたのか見えなかった、鼻の低いしかしながら、血色のいい、男好きらしい丸顔の女であったが、この一年足らずの間に人が変ったかと見えるくらい肥っている。娘盛りの火のような圧迫に身体がうずいているように見える……この女の肉体の変化は予をしていろいろの空想を起さしめた。 出ようか出まいかと考えていると――死のうか死ぬまいかという問題が、出ようか出まいかの問題に移って、ここに予の心理的状態が変化した。水をかぶって上った時、予の心はよほど軽かった。そして体重を計ると十二貫二百匁あった。先日より四百匁増えている。 煙草に火をつけて湯屋を出ると、湯上りの肌に空気が心地よく触る。書くのだ! という気が起った。そして松屋へ行って原稿紙を買った。 部屋へ帰って間もなく宮崎君の手紙が着いた。 予は……! 宮崎君は、六月になったら予の家族を東京によこしてくれるという。旅費も何も心配しなくてもいいという…… ―――――――――――――― 今日予は全く自分の気分を明るくしようしようということばかりに努めて日を送ったようなものだ。頭が少し痛くってややもすると世界が暗くなるような気がした。 社から帰って来て飯を食っていると金田一君が来た。やはり勉強したくない晩だという。 「今夜だけ遊ぼう!」 そして二人は八時頃家を出て、どこへ行こうとも言わずに浅草へ行った。電気館の活動写真を見たが興がないので間もなく出て、そして塔下苑を歩いた。なぜか美しい女が沢山眼についた。とある所へ引っ張り込まれたが、そこからはすぐに逃げた。そしてまた別の所へ入ると、「ゼスチュア」に富んだ女がしきりに何か奢ってくれと言う。「弥助」を食った。 「新松緑!」それはいつか北原と入って酒を飲んだ所だ。二人は十時半頃にそこへ入った。たま子という女は予の顔に見覚えがあると言った。美しくて、そして品のある(言葉も)女だ。その女がしきりにその境遇についての不平と 否! 予は何ということもなく我が身の置き所が世界中になくなったような気持ちに襲われていた。「頭が痛いから今夜だけ遊ぼう!」それはウソに違いない。そんなら何を予は求めていたろう? 女の肉か? 酒か? 恐らくそうではない! そんなら何か? 自分にもわからぬ! 自意識は予の心を深い深いところへ連れて行く。予はその恐ろしい深みへ沈んで行きたくなかった。ウチへは帰りたくない。何かいやなことが予を待ってるようだ。そして本郷がバカに遠い所のようで、帰って行くのがおっくうだ。そんならどうする? どうもしようがない。身の置き所のないという感じは、予をしていたずらにバカな真似をせしめた。 「わたし、来月の五日にここを出ますわ、」とたま子が悲しそうな顔をして言った。 「出るさ! 出ようと思ったらすぐ出るに限る。」 「でも借金がありますもの。」 「いくら?」 「入るとき四十円でしたが、それがあなた、段々積もって百円にもなってるんでございますわ。着物だって一枚もこしらえはしないんですけれど……」 予はもう堪えられなくなるような気がした。泣くか、冗談を言うか、外に仕方がないような気持ちだ。しかし予はその時冗談も言えなかった。無論泣けなかった。 帳場ではたまちゃんの悪口を言ってる女将の声。そとには下卑た浪花節とひょうきんなひやかし客の声と、空虚なところから出るような女芸人の歌の節! 「浮世小路! ね!」と予は金田一君に言った。 酒を命じた。そして予は三杯グイグイ続けざまに飲んだ。酔いは忽ち発した。予の心は暗い淵へ落ちて行くまいとして病める鳥の羽ばたきするようにもがいていた。 イヤな女将が来た。予は二円出した。そして隣室に行っておえんという女と五分間ばかり寝た。たまちゃんが迎えに来て先の部屋に行った時は、金田一君は横になっていた。予はものを言いたくないような気持ちだった。……とうとう淵へ落ちたというような…… 出た。電車は車坂迄しかなかった。二人は池之端から歩いて帰った。予は友によりかかりながら言い難き悲しみの道を歩くような気持ち。酔ってもいた。 「酒を飲んで泣く人がある。僕は今夜その気持ちが分ったような気持ちがする。」 「ああ!」 「家へ行ったら僕を抱いて寝てくれませんか?」 二人は医科大学の横の暗闇を「青い顔」の話をしながら歩いた。 帰って来て門を叩くとき、予は自分の胸を叩いてイヤな音を聞くような気がした。 二十七日 火曜日 ハッと驚いて眼をさますと枕元におきよが立っていた。泣きたい位眠いのを我慢してハネ起きた。 曇った日。 昨夜のことがつまびらかに思い出された。予がおえんという女と寝たのも事実だ。その時何の愉快をも感じなかったのも事実だ。再び予があの部屋に入って行った時、たまちゃんの頬に微かに紅を そして今朝予は、今後決して女のために金と時間を費やすまいと思った。つまり仮面だ。 ―――――――――――――― 社に行っても四時頃まで予は何となく不安を感じていた。それは来月分の二十五円を前借しようしようと思って、下まで行きながら言い出しかねていたからだ。四時には社の金庫が閉まる。カン、カン……と頭の上の時計が四時を打った時、予はホッと息をついて安心した。 ―――――――――――――― 原稿紙を延べて心を鎮めていると窓ガラスにチラリと赤い影が映った。と同時に半鐘の音。八時ごろであった。窓から真向かいの小石川に火事が起ったのだ。火は勢いよく燃え、どことなく町の底が騒がしくなった。火! 予は近頃にない快いものを見るように窓を開け放して眺めた。 九時半頃電話口へ呼び出された。相手は金田一君。中島君等と日本橋の松花亭という料理屋に来ているが、来ないかという。早速出かけた。 四十分も電車に揺られて目指す家に行くと、男四人に若い芸者一人、鼻の内山が柄にない声を出して新内か何かを歌っていた。 一時間ばかり経ってそこを出、金田一君と二人電車に乗って帰ってきた。 二十八日 水曜日 崖下の家では幟を立てた。若葉の風が風車を廻し、鯉と吹き流しを葉桜の上に泳がせている。 早く起きて、麻布霞町に佐藤氏を訪ね、来月分の月給前借のことを頼んだ。今月はダメだから来月のはじめ迄待ってくれとのことであった。電車の往復、どこもかしこも若葉の色が眼を射る。夏だ! 社に行って何の変ったことなし。昨夜最後の一円を不意の宴会に使ってしまって、今日はまた財布の中にひしゃげた五厘銅貨が一枚。 明日の電車賃もない。 二十九日 木曜日 休むことにした。そして小説「底」を書き始めた。十二時過ぎても出かけないので金田一君が来た。 「あなた、電車賃がなくってお出かけにならないのじゃありませんか?」 「いいえ、それもそうですが……許して下さい。今日はバカに興が湧いてきたんです。」 「そうですか! そんなら折角。」 こう言って友は出て行った。 午後二時間ばかり佐藤衣川に邪魔せられたほか、予は休みなくペンを動かした。 そして夜は金田一君の部屋で送った。 三十日 金曜日 今日は社に行っても煙草代が払えぬ。前借は明日にならなくてはダメだ。家にいると晦日だから下からの談判が怖い。どうしようかと迷った末、やはり休むことにした。 「底」を第三回まで書いた。 この頃すみちゃんという背の低い女の子が来た。年は十七だというが、身体は十四位にしか見えぬ。この女が昨夜ちょっと家へ行って母親に叱られ、兄に何とか言われて飛び出し、死ぬつもりで品川の海岸まで行ったが、とうとう死なずに一人帰って来たという。ここまで来た時は三時半頃だったという。 恐ろしい意志の強い、こましゃくれた、そのくせ可愛い女だ。「おきよさんは可愛い娘ね」と自分より年上の女中のことを言う。「それ何だっけ――おつねさんか! あの人の顔はこんな風だわね、」とヒョットコの真似をしてみせる。 夜になると果たして催促が来た。明日の晩まで待たせることにする。 九時頃金田一君が二円五十銭貸してくれた。そのときから興が去った。寝て、枕の上で、二葉亭訳のツルゲーネフの「ルーヂン」を読む。 深い感慨を抱いて眠った。 五 月 東 京 一日 土曜日 昨日は一日、ヌカのような雨が降っていたが、今日はきれいに晴れて、久しぶりに富士を眺めた。北の風で少し寒い。 午前は「ルーヂン、浮草」を読んで暮した。ああ! ルーヂン! ルーヂンの性格について、考えることは、即ち予自身がこの世に何も起し得ぬ男であるということを証明することである。…… 社に行くと佐藤さんは休み。加藤校正長は何だかむくんだような顔をしていた。わざと昨日休んだ言い訳を言わずに、予も黙っていてやった。 前借は首尾よく行って二十五円借りた。今月はこれでもう取る所がない。先月の煙草代一円六十銭を払った。 六時半に社を出た。午前に並木君が来て例の時計の話があったので、その二十五円の金をどう処分すればいいか――時計を受けると宿にやるのが足らなくなり、宿に二十円やれば時計はダメだ――この瑣末な問題が頭いっぱいにはだかって容易に結末がつかない。実際この瑣末な問題は死のうか死ぬまいかということを決するよりも予の頭に困難を感じさせた。とにかくこれを決めなければ家へ帰れない。 尾張町から電車に乗った。それは浅草行きであった。 「お乗換は?」 「なし。」 こう答えて予は「また行くのか?」と自分に言った。 雷門で降りて、そこの牛屋へ上って夕飯を食った。それから活動写真へ入ったがちっとも面白くない。「スバル短歌号」を雑誌屋で買った。 「行くな! 行くな!」と思いながら足は千束町へ向かった。常陸屋の前をそっと過ぎて、金華亭という新しい角の家の前へ行くと、白い手が格子の間から出て予の袖を捕えた。フラフラとして入った。 ああ! その女は! 名は花子。年は十七。一目見て予はすぐそう思った。 「ああ! 小奴だ! 小奴を二つ三つ若くした顔だ!」 程なくして予は、お菓子売りのうす汚い婆さんとともに、そこを出た。 そして方々引っ張り廻されての挙句、千束小学校の裏手の高い煉瓦塀の下へ出た。細い小路の両側は戸を閉めた裏長屋で、人通りは忘れてしまったように無い。月が照っている。 「浮世小路の裏へ来た!」と予は思った。 「ここに待ってて下さい。私は今戸をあけてくるから、」とばあさんが言った。何だかキョロキョロしている。巡査を恐れているのだ。 死んだような一棟の長屋のとっつきの家の戸を静かに開けて、婆さんは少し戻って来て予を月影に小手招ぎした。 婆さんは予をその気味悪い家の中へ入れると、「私はそこいらで張り番していますから、」と言って出て行った。 花子は予よりも先に来ていて、予が上るが否や、いきなり予に抱きついた。 狭い、汚い家だ。よくも見なかったが、壁は黒く、畳は腐れて、屋根裏が見えた。そのみすぼらしい有様を、長火鉢の猫板の上に乗っている豆ランプがおぼつかなげに照らしていた。古い時計がものうげになっている。 煤びた隔ての障子の陰の二畳ばかりの狭い部屋に入ると、床が敷いてあった――少し笑っても障子がカタカタ鳴って動く。 微かな明りにジッと女の顔を見ると、丸い、白い、小奴そのままの顔がうす暗い中にポッと浮かんで見える。予は眼も細くなるほどうっとりとした心地になってしまった。 「小奴に似た、実に似た!」と、幾度か同じことばかり予の心はささやいた。 「ああ、こんなに髪がこわれた。イヤよ、そんなに私の顔ばかり見ちゃ!」と女は言った。 若い女の肌はとろけるばかり温かい。隣室の時計はカタッカタッと鳴っている。 「もう疲れて?」 婆さんが静かに家に入った音がして、それなり音がしない。 「婆さんはどうした?」 「台所にかがんでるわ。きっと。」 「可哀そうだね。」 「かまわないわ。」 「だって可哀そうだ!」 「そりゃ可哀そうには可哀そうよ。本当の独り者なんですもの。」 「お前も年をとるとああなる。」 「イヤ、わたし!」 そしてしばらく経つと、女はまた、 「いやよ、そんなにわたしの顔ばかり見ちゃ。」 「よく似てる」 「どなたに?」 「俺の妹に。」 「ま、うれしい?」と言って花子は予の胸に顔を埋めた。 不思議な晩であった。予は今まで幾度か女と寝た。しかしながら予の心はいつも何物かに追っ立てられているようで、イライラしていた。自分で自分をあざ笑っていた。今夜のように眼も細くなるようなうっとりとした、縹渺とした気持ちのしたことはない。 予は何ごとをも考えなかった。唯うっとりとして、女の肌の温かさに自分の身体まであったまってくるように覚えた。そしてまた、近ごろはいたずらに不愉快の感を残すに過ぎぬ○○○、この晩は○○○○○○のみ過ぎた。そして予は後までも何の厭な気持ちを残さなかった。 一時間経った。夢の一時間が経った。予も女も起きて煙草を喫った。 「ね、ここから出て左へ曲って二つ目の横町の所で待ってらっしゃい!」と女はささやいた。 シンとした浮世小路の奥、月影水のごとき水道のわきに立っていると、やがて女が小路の薄暗い片側を下駄の音かろく駆けて来た。二人は並んで歩いた。時々そばへ寄って来ては、「ほんとにまたいらっしゃい。ね!」 ―――――――――――――― 宿に帰ったのは十二時であった。不思議に予は何の後悔の念をも起さなかった。「縹渺たる気持ち」がしていた。 火もなく、床も敷いてない。そのまま寝てしまった。 二日 日曜日 お竹が来て起した。「あのね、石川さん、旦那が今お出かけになるところで、どうでしょうか、聞いて来いって!」 「あーあ、そうだ。昨夜はあんまり遅かったから、そのまま寝た、」と言いながら、予は眠い眼をこすりながら財布を出して二十円だけやった。「後はまた十日ごろまでに、」「そうですか!」とお竹は冷やかな、しかし賢こそうな眼をして言った。「そんなら貴方そのことをご自分で帳場におっしゃって下さいませんか? 私どもはただもう叱られてばかりいますから、」 予はそのまま寝返りを打ってしまった。 「あーあ、昨夜は面白かった!」 九時頃であった。小さい女中が来て、「岩本さんという方がおいでになりました、」と言う。岩本! はてな? 起きて床を上げて、呼び入れると果たしてそれは渋民の役場の助役の息子――実君であった。宿を同しくしたという徳島県生まれの一青年を連れて来た。 実君は横浜にいるおばさんを頼って来たのだが、二週間置いてもらった後、国までの旅費をくれて、出されたのだという。それで、国へは帰りたくなく、是非東京で何か職に就くつもりで三日前に神田のとある宿屋についたが、今日まで予の住所が知れぬので苦心したという。も一人の清水という方は、これもやはり家と喧嘩して飛び出して来たとのこと。 夏の虫は火に迷って飛び込んで死ぬ。この人達も都会というものに幻惑されて何も知らずに飛び込んで来た人達だ。やがて焼け死ぬか、逃げ出すか。二つに一つは免れまい。予は異様なる悲しみを覚えた。 予はその無謀について何の忠告もせず、「焦るな。のんきになれ」ということを繰り返して言った。この人達の前途にはきっと自殺したくなる時期が来ると思ったからだ。実君は二円三十銭。清水は一円八十銭しか持っていなかった。 清水君と予とは何の関係もない。二人一緒にでは今後実君を救うとき困るかも知れぬ。しかし予はその正直らしい顔の心細げな表情を見てはこのまま別れさせるには忍びなかった。 「宿屋の方はどうしてあるんです? いつでも出られますか?」 「出られます。昨夜払ってしまったんです……今日は是非どうかするつもりだったんです。」 「それじゃ――とにかくどっか下宿を探さなくてはならん。」 十時半頃予は二人を連れて出かけた。そして方々探した上で、弓町二ノ八豊鳴館という下宿を見つけ、六畳一間に二人、八円五十銭ずつの約束を決め、手附として予は一円だけ女将に渡した。 それから例の天ぷら屋へ行って三人で飯を食い、予は社を休むことにして、清水を宿へ荷物を取りにやり、予は実君を連れて新橋のステーションまで、そこに預けてあるという荷物を受け取りに行った。二人が引き返して来た時は清水はもう来ていた。予は三時ごろ迄そこでいろいろ話をして帰って来た。予の財布はカラになった。 ―――――――――――――― 今日予が実君から聞かされた渋民の話は予にとっては耐え難きまでいろいろの記憶を呼び起させるものであった。小学校では和久井校長と信子さんとの間に妙な関係が出来、職員室でヤキモチ喧嘩をしたこともあるという。そして去年やめてしまった信子さんは、どうやら腹が大きくなっていて、近ごろは少し気が変だという噂もあるとか! 沼田清民氏は家宅侵入罪で処刑を受け、三ヵ年の刑の執行猶予を得てるという。そのほかの人達の噂、一つとして予の心をときめかせぬものはなかった。――我が「蛍の女、」いそ子も今は医者の弟の妻になって弘前にいるという! 予の小説鳥影はまた案外故郷の人に知られているとのことだ。 夜、予は岩本の父に手紙を書こうとした。何故か書けなかった。札幌の智恵子さんに書こうとしたがそれも書けず、窓を開くと柔らかな夜風が熱した頬を撫でて、カーブにきしる電車の響きの底から故郷のことが眼に浮んだ。 三日 月曜日 社には病気届をやって、一日寝て暮した。お竹の奴バカに虐待する。今日は一日火も持って来ない。すみちゃんがチョイチョイ来ては罪のないことをしゃべって行く。それをらくちゃんの奴め、胡散臭そうな目をして見て行く。 イヤな日! 絶望した人のように疲れきった人のように、重い、頭を枕にのせて……客は皆断らせた。 四日 火曜日 今日も休む。今日は一日ペンを握っていた。「鎖門一日」を書いてやめ、「追想」を書いてやめ、「面白い男?」を書いてやめ、「少年時の追想」を書いてやめた。それだけ予の頭が動揺していた。遂に予はペンを投げ出した。そして早く寝た。眠られなかったのは無論である。 夕方であった、並木が来たっけ。それから岩本と清水がちょっと来て行った。やっぱり予はのんきなことばかり並べてやった。 五日 水曜日 今日も休む。 書いて、書いて、とうとう纏めかねて、「手を見つつ」という散文を一つ書き上げたのが、もう夕方。前橋の 六日 木曜日 今日も休む。昨日今日せっかくの靖国神社の祭典を日もすがらの雨。 朝、岩本、清水の二人に起された。何となく沈んだ顔をしている。 「このままではどうもならない! どうかしなければならぬ!」と予は考えた。 「そうだ! あと一週間ぐらい社は休むことにして、大いに書こう。それにはここではいけない。岩本の宿のあき間に行って、朝っから晩まで書こう。夜に帰って来て寝よう。」 そして金が出来たら三人でとりあえず、自炊しようと考えた。金田一君にも話して同意を得た。 原稿紙とインクを持って早速弓町へ行った。しかしこの日は何にも書けず、二人からいろいろの話を聞いた。聞けば聞くほど可愛くなった。二人は一つ布団に寝、二分芯のラムプを灯して、その行末を語り合っているのだ。 清水茂八というのも正直な、そしてなかなかしっかりしたところのある男だ。二年ばかり朝鮮京城の兄の店に行っていたのを、是非勉強しようと思って逃げて来たのだという。 予は頭の底にうずまいているいろいろの考えごとを無理に押さえつけておいて、二人の話を聞いた。清水は朝鮮の話をする。予はいつしかそれを熱心になって聞いて、「旅費がいくらかかる?」などと問うてみていた。哀れ! 夜八時頃帰って来、一寸金田一君の部屋で話して帰って寝た。 今日書こうと思い立ったのは、予が現在に於いてとり得るただ一つの道だ。そう考えると悲しくなった。今月の月給は前借してある。どこからも金の入りようがない。そして来月は家族が来る……予は今底にいる――底! ここで死ぬかここから上って行くか。二つに一つだ。そして予はこの二人の青年を救わねばならぬ! 七日 金曜日 七時頃に起してもらって、九時には弓町へ行った。そして本を古本屋へ預けて八十銭を得、五分芯のラムプと将棋と煙草を買った。桔梗屋の娘! 話ばかり栄え、それに天気がよくないので、筆は進まなかった。それでも「宿屋」を十枚ばかり、それから「一握の砂」というのを別に書き出した。とにかく今日はムダには過ごさなかった。夜九時ごろ帰った。桔梗屋の娘! 岩本の父から手紙。何分頼むとのこと。それから釧路の坪仁子のなつかしい手紙、平山良子のハガキ、佐藤衣川のハガキなどが来ていた。 八日 土曜日――十三日 木曜日 この六日間予は何をしたか? このことは遂にいくら焦っても現在をぶち壊すことの出来ぬを証明したに過ぎぬ。 弓町に行ったのは、前後三日である。二人の少年を相手にしながら書いてはみたが、思うようにペンが捗らぬ。十日からは行くのをやめて、家で書いた。「一握の砂」はやめてしまって「札幌」というのを書き出したが、五十枚ばかりでまだ纏まらぬ。 社のほうは病気のことにして休んでいる。加藤氏から出るように行って来たのにも腹が悪いという手紙をやった。そして、昨日、弓町へ行くと二人は下宿料の催促に弱っているので、岩本を使いにやって加藤氏に佐藤氏から五円借りてもらい、それを下宿へ払ってやった。北原から贈られた「邪宗門」も売ってしまった。 清水にはいろいろ苦言して、予からその兄なる人に直接手紙をやり、本人には何でも構わず口を求める決心をさせた。岩本の方は平出の留守宅へ書生に周旋方を頼んでおいた。 限りなき絶望の闇が時々予の眼を暗くした。死のうという考えだけはなるべく寄せ付けぬようにした。ある晩、どうすればいいのか、急に眼の前が真っ暗になった。社に出たところで仕様がなく、社を休んでいたところでどうもならぬ。予は金田一君から借りて来てる剃刀で胸に傷をつけ、それを口実に社を一ヶ月も休んで、そして自分の一切をよく考えようと思った。そして左の乳の下を斬ろうと思ったが、痛くて斬れぬ。微かな傷が二つか三つ付いた。金田一君は驚いて剃刀を取り上げ、無理矢理に予を引っ張って、インバネスを質に入れ、例の天ぷら屋に行った。飲んだ。笑った。そして十二時ごろに帰って来たが、頭は重かった。明りを消しさえすれば目の前に恐ろしいものがいるような気がした。 母からいたましいカナの手紙がまた来た。先月送ってやった一円の礼が言ってある。京子に夏帽子をかぶせたいから都合よかったら金を送ってくれと言って来た。 このまま東京を逃げ出そうと思ったこともあった。田舎へ行って養蚕でもやりたいと思ったこともあった。 梅雨近い陰気な雨が降り続いた。気の腐る幾日を、予は遂に一篇も脱稿しなかった。 友人には誰にも会わなかった。予はもう彼らに用がない。彼らもまた予の短歌号の歌をよんで怒ってるだろう。 渋民のことが、時々考えられた。 あんなにひどく心を動かしたくせに、まだ妹にハガキもやってない。岩本の父にはハガキだけ。家にもやらぬ。そして橘智恵子さんにもやらぬ。やろうと思ったが何も書くことがなかった! 今夜は金田一君の部屋へ行って女の話が出た。頭が散っていて何も書けぬ。帰って来て矢野龍渓の「不必要」を読んで寝ることにした。時善と純善! その純善なるのも畢竟何だ? 予は今予の心に何の自信なく、何の目的もなく、朝から晩まで動揺と不安に追っ立てられていることを知っている。何のきまったところがない。この先どうなるのか? 当てはまらぬ、無用な鍵! それだ! どこへ持って行っても予のうまく当てはまる穴がみつからない! 煙草に餓えた。 十四日 金曜日 雨。 佐藤衣川に起された。五人の家族をもって職を探している。 佐藤が帰って清水が来た。日本橋のある酒屋の得意廻りに口があるという。 岩本を呼んで履歴書を書いてくるように言ってやった。 いやな天気だが、何となく心が落ち着いてきた。社を休んでいる苦痛も馴れてしまってさほどでもない。その代り頭が散漫になって何も書けなかった。何だかいやに平気になってしまった。 二度ばかり口の中から夥しく血が出た、女中はノボセのせいだろと言った。 夜は「字音仮名遣便覧」を写した。 渋民村を書こうと思ったが、どうしても興が湧かなかったからそのまま寝てしまった。 十五日 土曜日 九時に岩本に起された。岩本の父から「よろしくたのむ」という手紙が来た。 今日の新聞は長谷川辰之助氏(二葉亭四迷)が、帰朝の途、船の中で死んだという報を伝え、競ってその徳を讃え、この何となく偉い人を惜しんでいる。 この頃は大分寒かったが、今日から陽気が直った。雨も晴れた。 何もせずに一日を過ごした。緩み果てた気の底から、遠からず恐ろしいことを決行せねばならぬような感じがチラチラ浮かんでくる。 夜、二人の少年がやって来た。清水は京橋の酒屋へ丁稚に住み込むことに決まって、明日のうちに行くという。 二人が帰って間もなく、いつか来たっけ小原敏麿という兎みたいな眼をした文士が来た。ウンザリしてしまってロクに返事もしないでいると、何のカンのとつまらぬことをしゃべり散らして十時半頃に帰って行った。 「ものは考えよう一つです、」とその男が言った。「人は五十年なり六十年なりの寿命を一日、一日減らしていくように思ってますが、僕は一日一日新しい日を足していくのがライフだと思ってますから、ちっとも苦しくも何とも思わんです。」 「つまりあなたのような人が幸福なんです。あなたのように、そうごまかして安心して行ける人が……」 十一時頃、金田一君の部屋に行って二葉亭氏の死について語った。友は二葉亭氏が文学を嫌い――文士と言われることを嫌いだったというのが解されないと言う。憐れなるこの友には人生の深い憧憬と苦痛とはわからないのだ。予は心に堪えられぬ淋しさを抱いてこの部屋に帰った。遂に、人はその全体を知られることは難い。要するに人と人との交際はうわべばかりだ。 互いに知り尽していると思う友の、遂にわが底の悩みと苦しみとを知り得ないのだと知った時のやる瀬なさ! 別々だ、一人一人だ! そう思って予は言い難き悲しみを覚えた。 予は二葉亭氏の死ぬ時のこころを想像することが出来る。 十六日 日曜日 遅く起きた。雨が降りこめてせっかくの日曜が台無し。 金田一君の部屋へ行って、とうとう、説き伏せた。友をして二葉亭を諒解せしめた。今日も岩本が来た。 社にも行かず、何もしない。煙草がなかった。つくねんとして又田舎行きのことを考えた。国の新聞を出してみていろいろと地方新聞の編集のことを考えた。 夕方金田一君に現在の予の心を語った。「予は都会生活に適しない、」ということだ。予は真面目に田舎行きのことを語った。 友は泣いてくれた。 田舎! 田舎! 予の骨を埋むべき所はそこだ。俺は都会の激しい生活に適していない。一生を文学に! それは出来ぬ。やって出来ぬことではないが、要するに文学者の生活などは、空虚なものに過ぎぬ。 十七日 月曜日 午前は凄まじいばかり風が吹いた。休む。 午後、岩本がちょっと来て行った。 今日の新聞は二葉亭氏がニヒリストであったことや、ある身分卑しい女に関した逸話を掲げていた。 昼飯まで煙草を我慢していたが、とうとう「あこがれ」と他二三冊を持って郁文堂へ行き、十五銭に売った。「これはいくらなんだ?」と予は「あこがれ」を指した。 「五銭ですね、」と肺病患者らしい本屋の主人が言った。ハ、ハ、ハ、…… 今日も予は田舎のことを考えた。そしてそれだけのことに日を送った。「如何にして田舎の新聞を経営すべきか? 又、編集すべきか?」それだ! この境遇にいるこの予が一日何もせずに、こんなことを考えて暮したということは! 夜枕の上で「新小説」を読んで少しく思い当たることがあった。 「ナショナルライフ!」それだ。 三十一日 月曜日 二週間の間、ほとんどなすこともなく過した。社を休んでいた。 清水の兄から手紙は来たが、金は送って来ない。 岩本の父から二三度手紙。 釧路なる小奴からも手紙が来た。 予はどこへも――函館へも――手紙を出さなかった。 「岩手日報」へ「胃弱通信」五回ほど書いてやった。それは盛岡人の眠りをさますのが目的であった。反響は現れた。「日報」は「盛岡繁栄策」を出し始めた。 死刑を待つような気持ち! そう、予は言った。そして毎日独逸語をやった。別に、いろいろ工夫して、地方新聞の雛形を作ってみた。実際、地方の新聞へ行くのが一番いいように思われた。無論そのためには文学を棄ててしまうのだ。 一度、洋画家の山本鼎君が来た。写真通信社の話。 ―――――――――――――― 晦日は来た。 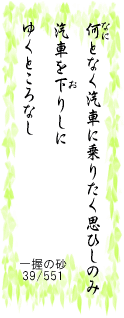 黙って家にもおられぬので、午前に出かけて羽織――ただ一枚の――を質に入れて七十銭をこしらえ、午後何のアテもなく上野から田端まで汽車に乗った。ただ汽車に乗りたかつたのだ。田端で畑の中の知らぬ道をうろついて土の香を飽かず吸った。 帰って来て宿へ申しわけ。 この夜、金田一君の顔の憐れに見えたつたらなかつた。 六月 東京 一日 火曜日 午後、岩本に手紙を持たしてやって、社から今月分二十五円を前借りした。但し五円は佐藤氏に払ったので手取り二十円。 岩本の宿に行って、清水と二人分先月分の下宿料(六円だけ入れてあった)十三円ばかり払い、それから、二人で浅草に行き活動写真を見てから西洋料理を食った。そして小遣い一円くれて岩本に別れた。 それから何とかいう若い子供らしい女と寝た。その次にはいつか行って寝た小奴に似た女――花――のとこへ行き、ヘンな家へおばあさんと行った。 おばあさんはもう六十九だとか言った。やがて花が来た。寝た。何故かこの女と寝ると楽しい。 十時頃帰った。雑誌を五六冊買ってきた。残るところ四十銭。 二十日間 (床屋の二階に移るの記) 本郷弓町二丁目十八番地 新井(喜之床)方 髪がボーボーとして、疎らな髭も長くなり、我ながらイヤになる程やつれた。女中は肺病やみのようだと言った。下剤を用い過ぎて弱った身体を十日の朝まで三畳半に横たえていた。書こうという気はどうしても起こらなかった。が、金田一君と議論したのが縁になって、いろいろ文学上の考えを纏めることが出来た。 岩本が来て予の好意を感謝すると言って泣いた。 十日の朝、盛岡から出した宮崎君と節子の手紙を枕の上で読んだ。七日に函館を発って、母は野辺地に寄り、節子と京子は友と共に盛岡まで来たという。予は思った。「遂に!」 宮崎君から送ってきた十五円で本郷弓町二丁目十八番地の新井という床屋の二階二間を借り、下宿の方は、金田一君の保証で百十九円余を十円ずつ月賦にしてもらい、十五日に発って来るように家族に言い送った。 十五日の日に 十六日の朝、まだ日の昇らぬうちに予と金田一君と岩本と三人は上野ステーションのプラットフォームにあった。汽車は一時間遅れて着いた。友、母、妻、子……車で新しい家に着いた。 (※ローマ字日記 完) 「明治四十三年四月より」にに続きます。 ページトップ |
||||||||||||||||||||||||||||||
石川啄木 啄木日記 |
||||||||||||||||||||||||||||||